
 |
|
<ホクレントップページ |
あぐりぽーと51号で農薬の必要性、安全性を紹介しました。本号では、農薬の知識をさらに深めていただくために、生物農薬の特徴を化学合成農薬と比べてご紹介します。生物農薬は、これを利用してもJAS有機農産物に認められ、"生物"がなんとなくよく響き、環境や安全を強く意識する皆さんの期待が高いようです。ただし、化学合成農薬と同レベルの使用基準設定、それを遵守の上での安全性担保に違いはありません。また、生物的効果故に気象等の影響を受け易く、安定効果の発揮には生産者の生物農薬等の十分な熟知と厳しい努力が求められます。本特集を参考に、農薬利用の賢明なレパートリーを広げてください。 |
|
|
新JAS法や北海道が進めているクリーン農業では、環境に対する負荷をより低減することを目標に、化学合成農薬の使用回数等が制限されています。しかし、農作物の生産は同一作物をある一定面積作付けするため、その作物に特有の害虫や病害の被害を受けやすくなります。また、生育初期においては裸地の部分が多いため雑草との競合も問題となります。そのため、クリーン農業等でも必要最小限の防除はどうしても必要となりますが、化学合成農薬を使用しない場合は生物農薬を使用することになり、そのような場面で生物農薬の使用が増加しています。
1)生物農薬の分類 生物農薬といっても色々な種類がありますが、大別すると、天敵昆虫(捕食性昆虫、寄生性昆虫などで、捕食性ダニ類も含む)、天敵線虫(昆虫寄生性線虫、微生物捕食性線虫など)、天敵微生物(細菌、糸状菌、ウイルス、原生動物など)に分けられます。 防除対象は主に害虫ですが、病害を防ぐものもあり、近年除草に使用できるものもでてきました。 日本植物防疫協会での分類は表1のようになっています。 2)生物農薬が効果を現す仕組み 生物農薬が効果を現す仕組みを以下に紹介します。また、現在日本で使用されている主な生物農薬を表2に示します。 1.天敵昆虫(写真) 捕食性昆虫(餌となる動物を昆虫が探して食べる)と寄生性昆虫(成虫が、寄主の昆虫に産卵し、孵化した幼虫が寄主の体を餌にして発育し、最終的には殺してしまう)に分けられます。捕食性昆虫(捕食性ダニを含む)は、テントウムシ、カブリダニ、カメムシなどがあります。寄生性昆虫はハチやハエが多く、オンシツツヤコバチは、施設野菜類のコナジラミ類の防除に使われます。 2.天敵線虫 防除に使われるのは体長1mm以下の昆虫寄生性線虫です。天敵線虫は土壌中で害虫の幼虫の口などから体内に入り、線虫が自分の腸の中にもっている共生細菌を放出し、その細菌の毒素により害虫は敗血症を起こし死んでしまいます。死亡した幼虫の体内で増殖した線虫は土壌中に出て次々と別の幼虫の体内に入って増殖するため殺虫効果が持続します。 3.微生物 ア.殺虫剤 天敵微生物の代表は、バチルス・チューリンゲンシス(Bacillus thuringiensis: BT)という枯草菌の一種が産生する結晶性毒素で、殺虫剤として使われています。昆虫がBT剤のついた餌を食べると、アルカリ条件下の消化管のなかで分解酵素により毒素が活性化され、消化管を破壊し殺虫力を示すようになります。しかし、ミツバチのように消化管の中がアルカリ性でない昆虫や胃液が酸性の哺乳類では毒性を現しません。BT剤はその種類により、コナガ、モンシロチョウなどに効くもの、ハエ、カに効くもの、甲虫に効くものがあります。 イ.殺菌剤(図2) バチルス・ズブチリス(Bacillus subtilis)は、病原菌を直接攻撃する力はありませんが、ある種の病原菌とは植物の表面で住む場所と栄養の奪い合いをするため、結果的に後からきた病原菌は住む場所やえさが得られないため定着できず、植物は病原菌からガードされます。現在、日本では、野菜類等の灰色かび病、うどんこ病等の防除剤として農薬登録されています。 ウ.除草剤 ザントモナス・キャンペストリス(Xanthomonas campestris)という細菌は、芝生の雑草であるスズメノカタビラの茎や葉の傷口から侵入し、水分や栄養を体内に運ぶ導管を目詰まりさせ、最終的には枯死させてしまいます。 エ.その他 ・かび(糸状菌) かび(糸状菌)は接触や風に乗って胞子が広がってきます。昆虫の体に付着すると胞子は菌糸を虫の表皮に密着させ、突起を体のなかに差し込み体液などを吸収し、さらに菌糸が体内で増殖して虫は死んでしまいます。高価な漢方薬の「冬虫夏草」は、このようにしてガの幼虫に糸状菌が感染してできたものです。桑や柑橘類の害虫のカミキリムシ類を対象にした糸状菌製剤が農薬登録されています。 ・ウイルス ウイルスは昆虫にも感染し、あるウイルスが感染すると昆虫は死んでしまいます。このような病原ウイルスのなかから、標的以外の生物に悪影響を及ぼさないウイルスが選ばれ殺虫剤として使われます。多く使われているのは、バキュロウイルス(Baculovirus)属の核多角体病ウイルス(NVP)、顆粒病ウイルス(GV)、サイポウイルス(Cypovirus)属の細胞質多角体病ウイルスです。 また、ウイルスは病害防除にも使われます。これは植物がすでに感染しているウイルスと同じか、極めて近縁のウイルスには感染しにくいという「干渉作用」を利用したものです。弱毒ウイルスとしてトマトのタバコモザイクウイルス、きゅうりの緑斑モザイクウイルスなどの予防に使われています。 3)生物農薬の長所と短所 1.長所 もともと、自然界に存在する生物を利用しているため、以下の長所があるとされています。 ・環境に対する影響が少ない。 ・人畜に対する薬害、収穫物への残留毒性の心配が少ない。 ・抵抗性が発達しにくい。 ・防除対象となる生物だけに効くため、リサージェンス(薬剤散布後の対象防除害虫の爆発的増加)の問題がない。 ・クリーンなイメージがあり、有機農産物にも使用可能である。 ・必要とされる毒性試験項目が少なく、開発コスト比較的安価に抑えられる。 |
2.短所
・長所と一部裏腹な面がありますが、以下の短所が考えられます。 ・防除対象となる生物にしか効かないため、使用場面が限定される。 ・効果が緩やかで速効性に欠け、化学合成農薬と比べて効果が不安定である。 ・現場での使用方法が難しい。 ・製造技術(大量増殖、安定製剤化等)が難しく、そのために製品価格が高い。 ・在来種以外の天敵昆虫の導入は、在来種との競合により本来の生態系のバランスを崩す恐れがある。 4)生物農薬の使用上の注意事項 1.天敵昆虫は特に種特異性が高く、1種類の天敵は1種類の害虫にしか効果を示しません。このことは環境に対する調和度が高い反面、防除対象が限定され、コスト高となるという二面性があります。 2.天敵昆虫の多くはヨーロッパからの導入種であり、これらがハウスを抜け出し日本の生態系に与える影響については充分に検証されていません。 3.生物農薬は効果が緩やかで速効性に欠けるため、病害虫多発時には化学合成農薬を用いる等、的確なアドバイスが必要となります。 4.生物農薬は生きているものも多く、その場合は低温で輸送し到着後すぐ全量使い切りというのが基本となっています。 5.急な需要にも対応しにくいため、精確な受注生産、迅速な農家までの配送を必要とし、流通コストも高いものとなっています。 6.防除効果は環境に左右される事が多いため、ある作物・場所・時期においては効果があっても、別の条件では効果が低いこともあります。 7.大量増殖技術や製品の安定性などの製造技術が難しいことも、精確な受注生産が必要な要因となっています。 8.以上のことから、生物農薬は使用方法が難しく単に化学合成農薬の代替とはならず、それぞれの生物としての特性を十分に把握して使用しなくては充分な効果をあげることは難しいものとなっています。 5)生物農薬使用時における失敗要因 実際に圃場で生物農薬の効果を安定的に発揮するためには、化学合成農薬以上に生物農薬の特性や使用方法を熟知していなければなりません。その知識はこれまでの化学的防除に関するものと全く異なっていたり、場合によっては化学的防除では考えられなかった発想の転換を迫られることもあります。 生物農薬(主に天敵)使用における失敗要因としては、以下の項目があります。 ・天敵放飼の前後に、天敵に影響のある化学合成農薬を散布した。 ・散布タイミングが遅れ、害虫密度が高い状態で放飼したため、抑制しきれなかった。生物農薬は化学合成農薬のようなパンチ力はない。 ・購入した苗に既に化学合成農薬が散布されていた。 ・到着した日に放飼しなかった。天敵は生き物であり、放飼が遅れると弱る。 ・天敵が定着できない温度(厳寒期・酷暑期)に導入した。
生物農薬が普及しているヨーロッパは気候が冷涼であり、閉鎖度の高い大型ガラス室で栽培され、環境の変動も大きくありません。また、日本に比べて病害虫の種類が少ないため、主要な害虫を天敵により防除することが可能との考えのようです。 これに対し、日本は高温多湿な気候で地域や季節による環境の変動が大きく、しかも閉鎖度の低いビニールハウス栽培が主体で、環境条件の変動が千差万別です。また、病害虫の種類も多く、特定の数種のみを天敵等で防除し、他の病害虫の防除は化学合成農薬に頼らざるを得ません。 2)生物農薬の出荷動向 日本での生物農薬の出荷金額は農薬要覧(日本植物防疫協会発行)によると表3のとおりとなっています。化学合成農薬の出荷金額が減少している中で、生物農薬は増加傾向にあります。 分類でみるとBT剤が全体の約半分となっており、ここ数年は殺菌剤が増加しています。
平成15年12月に出された「クリーン農業技術体系」では、「YES! clean」表示制度での登録基準のなかで、化学合成農薬の使用回数(成分カウント)が示されました。作物、作型により多少の違いはありますが慣行栽培に対し化学合成農薬を概ね3〜5割低減することが「YES! clean」登録基準の条件とされました。ただし、登録基準のなかでカウントしない薬剤として、生物農薬や天然由来物質が認められており、「YES! clean」に取り組む際に化学合成農薬のみで防除体系を組むことが困難な場合、その補完として生物農薬を防除体系に組み入れることが多くなっています。
また、生物農薬による防除は一般的に化学合成農薬に比べて効果が低く、状況によっては効果が認められないこともあります。したがって、生物農薬を使いこなすには、病害虫・雑草の生態や生物農薬の特性・使用法を熟知しなければなりません。さらに、生物農薬に対する化学合成農薬の影響の程度までも考慮しなければなりません。 今後、病害虫・雑草の防除は耕種的、物理的、化学的、生物的防除を総合的に組み合わせ、より環境にやさしい体系を組み立てていく必要があります。生物農薬は、そのための有効な手段のひとつですが、対象病害虫の拡大、取扱い・使用方法の簡便化、価格の低減および他の防除方法との効果的な防除体系の確立が望まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

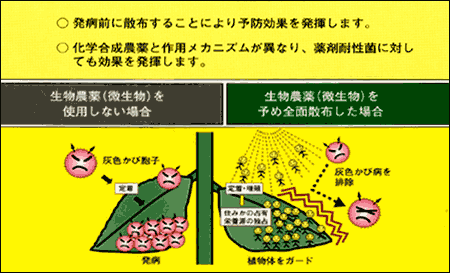
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る |