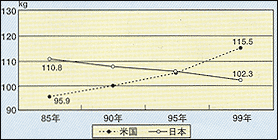1.野菜を取りまく環境
北海道産の野菜は、全国に出荷されており、日本の食料基地の一翼を担っている。
しかし、長引く景気低迷、野菜類の輸入急増のなかで、消費者意識や流通・消費構造が大きく変化し需要減や市況低迷が続き、産地にとっては大変厳しい販売環境となっている。
野菜の総生産量の動きからみると平成3年の1,527万トンが、平成12年には1,372万トンに減少し、この間輸入量は110万トンから224万トンと倍増している。野菜の自給率も90%が82%と低下している。(表1)
| |
H3年 |
H8年 |
H9年 |
H10年 |
H11年 |
H12年 |
| 作付面積 |
589 |
525 |
514 |
506 |
501 |
489 |
| 国内生産量 |
1,527 |
1,462 |
1,431 |
1,365 |
1,361 |
1,372 |
| 輸入量 |
110 |
180 |
172 |
196 |
220 |
224 |
| 自給率 |
90 |
86 |
86 |
84 |
83 |
82 |
|
| 注: |
国内生産量及び自給率は農林水産省「食料需給表」
(平成12年は速報)輸入量は財務省「貿易統計」 |
2.消費動向と需要拡大
ここ数年、国民の1人当たりの野菜消費量は減少の一途をたどり、肉が主食のイメージの強いアメリカをも下回っている(図1)。この野菜摂取の減少と反比例するように、糖尿や高血圧などの生活習慣病者が増加している。この現象に危機感を持った労働厚生省、農水省、文部省が共同で「食生活指針」を作成。それをうけて農水省は、医療、栄養、教育機関と連携し食育などを通して野菜摂取の習慣化をはかる活動を開始している。(表2、表3)
3.輸入急増に対処する産地構造改革計画
昨年、日本政府は、野菜輸入急増の対抗策として長ねぎ、しいたけ、畳表の輸出国である中国に対して、セーフガード暫定措置(4月23日〜11月20日)を発動した。一方、将来的に国内の野菜供給力を確保するために、消費者・実需者の求める良質野菜を安全供給できる産地の体力強化をはかっている。1つは、流通・消費を巻き込んだ産地戦略タイプ(低コスト化、契約取引推進、高付加価値化)を柱にした改革計画を作成し、その実践がすすめられている。さらに、卸売市場の制度改革や野菜生産出荷の安定制度の見直し、新たな契約野菜供給事業の創設など、生産・流通の両面からの構造改革が始まっており、いま、まさに全国の野菜生産が大きく変わろうとしている。
| 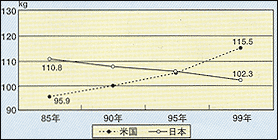
| 資料 |
: |
農林水産省「食料需給表」、FAO 'Food Balance Sheet' |
| 注 |
: |
供給純食料ベース。FAOによる米国のデータは、粗食料ベースであるため、粗食料ベースの日米の比率から純食料ベースを推計 |
| |
国内消費仕向量(万トン) |
1人当たり消費量(kg) |
| 平成9年度(基準年) |
1,669 |
101.9 |
| 11(現状) |
1,679 |
102.3 |
| 22(目標) |
1,725 |
108.0 |
|
| 食生活指針 |
食生活指針の実践(野菜関係) |
| 野菜・果実、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。 |
たっぷり野菜で、ビタミン、ミネラル、食物繊維をとりましょう。 |
| 緑黄色野菜などで、カルシウムを十分とりましょう。 |
|
| (平成12年3月:文部省・厚生省・農林水産省決定) |
4.産地に求められるもの
現在も北海道産野菜への消費地からの期待は強い。その期待に応えるためにも、輸入品に対抗できる低コスト化、実需者のニーズに応える計画的な供給、クリーン農業などによる良質で安全性が高く、消費者の信頼を得られる野菜の安定生産に、今こそ取組む必要がある。
|