
 |
|
<ホクレントップページ |
| 近頃、食料自給率向上、環境保全、家畜ふん尿処理、食料の安全性などが様々な面で課題となっている。この中であまり目立たないが、北海道では緑肥・飼料作物が重要な役割を果たしている。 すなわち、緑肥は「土づくり」だけでなく、土壌病害虫の防除や休閑地の被覆などに、飼料作物の増産は自給率向上やふん尿問題に深くかかわっている。 ここでは、この様な面からいくつかの作物を取り上げる。 |
|
|
北海道農業研究センター品質制御研究チーム長 中野 寛 世界各地で、多種多様な植物が緑肥・被覆作物として利用されている。マメ科植物に限ってみても、緑肥・被覆作物が36属74種も紹介されている。これだけ多岐にわたるのは、緑肥作物が「土づくり」の作物というだけでなく、様々な目的で栽培されているためであり、日本でも最近は同じような状況となってきた。 |
|
緑肥の栽培 地力維持には、畑地で毎年約1.5t/10aの有機物投入が要求されている。そのためには、テンサイ茎葉部など作物残渣だけでは足りず、堆肥や緑肥を鋤き込む必要がある。道内では、小麦やバレイショ等の後作に緑肥としてエン麦、シロカラシ、ヒマワリが栽培され、秋まき小麦の間作に赤クローバーが導入されている。 また、農家の耕地面積の増大につれ、「土づくり」のための休閑緑肥を夏作に栽培できる機会が増えてきている。 さらに、遊休化した農地をどう省力的に管理するかという問題も発生している。ソルゴーやトウモロコシなど大きく生長する作物を栽培して「土づくり」に、地表を早く被覆して雑草の生長を抑えるヘアリーベッチやファセリア(写真1)などと、目的に応じて各種の緑肥作物を選べるようになってきた。 また、北海道農業研究センター(旧農水省北海道農業試験場)が検討しているように、畑作物と飼料作物のアルファルファを輪作で栽培する体系など、地域に応じて作物の種類や使い方を工夫できる状況になっている。 
窒素・リン酸栄養 |
土壌の微生物バランス・対抗植物 連作による土壌病害は、糸状菌によるものが多い。連作や短期輪作を続けると、土壌中の微生物がバランスがくずれ糸状菌が増加し、病害が多発するようになる。一方、堆肥や緑肥などの有機物の鋤き込みによって、土壌中の微生物の種類が増え、病害の発生が抑制される。 特定の病虫害を抑える対抗植物としては、大根や長芋などの根菜類のキタネグサレセンチュウを抑える野生エン麦やマリーゴールド等が見出されてきた。美しいマリーゴールドの花は、景観植物としても活用できる。ダイズシスト線虫を抑えるには、秋小麦の間作緑肥として赤クローバーの栽培も有効であることが確認されている。 その他、アズキ落葉病やテンサイそう根病に対して野生エン麦が、インゲン根腐病にアルファルファの効果が高いという試験結果も得られている。 土壌浸食防止・リビングマルチ 春先、耕起して裸地状態になった火山灰土壌の畑では、強風により一日4トン/10a肥沃な表土が飛散して失われる(図3)。また、傾斜地では降雨によっても土壌浸食を受ける。 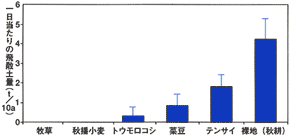 図3 土壌の侵食 強風時の土壌の飛散に対する前作の影響(十勝農試)
図3 土壌の侵食 強風時の土壌の飛散に対する前作の影響(十勝農試)
土壌保全型農業の試みとして、不耕起栽培が注目されているが、東北地方で行われた試験では、草丈の低いクローバを下草(リビングマルチ)にして不耕起栽培したトウモロコシの収量は、慣行栽培と同等であったという。この場合、クローバには土壌浸食を抑えるだけでなく、雑草抑制やトウモロコシの根域土壌を改善する役割も期待できる。 さらに、九州や四国の温暖地でも、施設栽培のトマトや露地の畑作物栽培で、夏場に枯れるヘアリーベッチをリビングマルチとして栽培すると、雑草防除、土壌水分の保持、日中の高地温の緩和など、ビニール資材等と同様に各種のマルチの効果が得られたとの報告がある。(写真2)。  写真2 ヘアリーベッチのリビングマルチ
写真2 ヘアリーベッチのリビングマルチクリーニング作物・有機農業 野菜栽培施設で、土壌に過剰に蓄積した養分を吸収させて除去するためのクリーニング作物として、ソルガムやイネ科牧草の中に適した草種が見いされている。 このように、緑肥作物という名前よりも環境保全作物とでも呼ぶ方が相応しいほど、最近は様々な目的で栽培されるようになっている。例えば、有機農産の認定を受けるために、3年間は無農薬・無化学肥料で栽培する必要があるが、有機農業でも緑肥作物を上手に使うことができよう。 |
|
|
戻る |