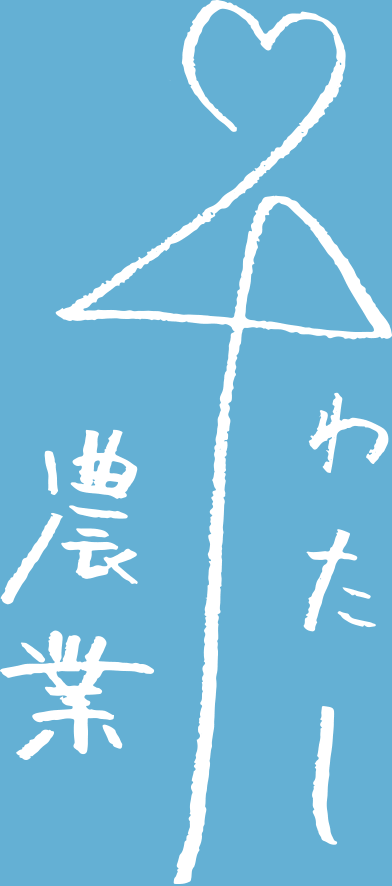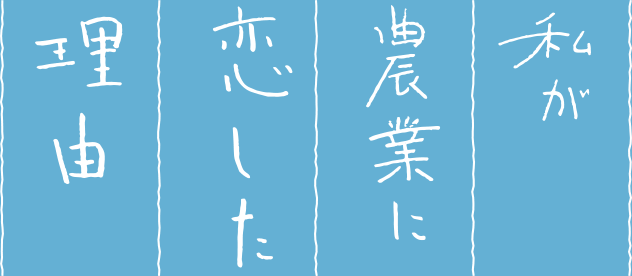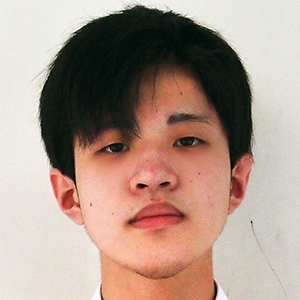こんにちは。高橋さん、増地さん、「MIRAI万博」での発表、お疲れさまでした。大舞台を終えた感想を聞かせてください。
こんにちは。高橋さん、増地さん、「MIRAI万博」での発表、お疲れさまでした。大舞台を終えた感想を聞かせてください。
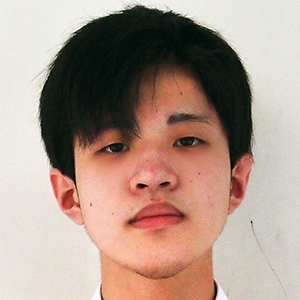 2000人の観客を前に、とても緊張しました。地域の問題に対して、具体的な解決策まで提示できたことが評価されたように感じました。
2000人の観客を前に、とても緊張しました。地域の問題に対して、具体的な解決策まで提示できたことが評価されたように感じました。
 会場の関係で、発表前のリハーサルがほとんどできず心配しましたが、更別村のPRができてうれしかったです。
会場の関係で、発表前のリハーサルがほとんどできず心配しましたが、更別村のPRができてうれしかったです。
 発表タイトルは「規格外品の可能性を求めて」ですが、規格外品に注目した経緯を教えてもらえますか。
発表タイトルは「規格外品の可能性を求めて」ですが、規格外品に注目した経緯を教えてもらえますか。
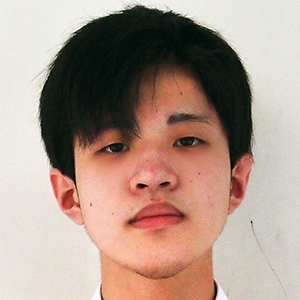 食料の約60%を輸入に頼っている日本は、食料輸送に伴うCO2を1690万t排出しています。その一方で、多くの規格外品が捨てられています。相反する状況を知った私たちは、地域の実態を把握しようと、JAさらべつや生産者さんを訪ね、お話を伺いました。すると、同JA管内の白菜と金時豆はいずれも20%以上が規格外品になっていることがわかりました。
食料の約60%を輸入に頼っている日本は、食料輸送に伴うCO2を1690万t排出しています。その一方で、多くの規格外品が捨てられています。相反する状況を知った私たちは、地域の実態を把握しようと、JAさらべつや生産者さんを訪ね、お話を伺いました。すると、同JA管内の白菜と金時豆はいずれも20%以上が規格外品になっていることがわかりました。

 ある白菜生産者さんの損失額を試算すると45万円以上で、規格外の白菜と金時豆をどうにか活用できないかと考えたのです。
ある白菜生産者さんの損失額を試算すると45万円以上で、規格外の白菜と金時豆をどうにか活用できないかと考えたのです。

 最初はどちらの作物から、活用法を検討したのですか。
最初はどちらの作物から、活用法を検討したのですか。
 金時豆を使ってビネガーを作るところからスタートしました。すでに先輩が「金時豆酢」の開発、商品化に成功していましたので、製造工程はそれを応用しつつ、使用する酵素の種類、配合割合、酵素が最も働く条件は実験を重ねました。最終的には、甘味やうま味を引き出すために、アミラーゼとペクチナーゼの2種類を使いました。
金時豆を使ってビネガーを作るところからスタートしました。すでに先輩が「金時豆酢」の開発、商品化に成功していましたので、製造工程はそれを応用しつつ、使用する酵素の種類、配合割合、酵素が最も働く条件は実験を重ねました。最終的には、甘味やうま味を引き出すために、アミラーゼとペクチナーゼの2種類を使いました。

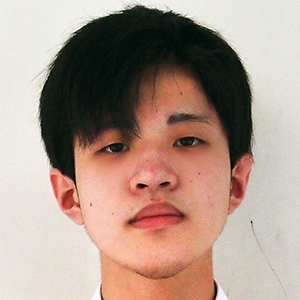 次に、金時豆ビネガーを使って、白菜の甘酢漬けを作り始めました。食品製造の教科書を見ながらの作業です。最初は味のまとまりがいまひとつでしたが、ビネガー、砂糖、ごま油に火を通し、砂糖をしっかり溶かすことでおいしくなりました。ただ、彩りが良くなく、これを解決するために加えたのが、村で生産しているすももです。
次に、金時豆ビネガーを使って、白菜の甘酢漬けを作り始めました。食品製造の教科書を見ながらの作業です。最初は味のまとまりがいまひとつでしたが、ビネガー、砂糖、ごま油に火を通し、砂糖をしっかり溶かすことでおいしくなりました。ただ、彩りが良くなく、これを解決するために加えたのが、村で生産しているすももです。

 漬け物にすももというのは、なかなか思いつきませんね。
漬け物にすももというのは、なかなか思いつきませんね。
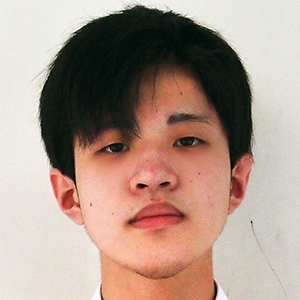 私も初めは抵抗がありました。酸味が強過ぎるのではないかとの意見が多かったからです。でも、加えて正解でした。更別村は、金時豆は生産量日本一、すももは村自慢の農産物です。これら2つを使っていることは、PRポイントにもなります。
私も初めは抵抗がありました。酸味が強過ぎるのではないかとの意見が多かったからです。でも、加えて正解でした。更別村は、金時豆は生産量日本一、すももは村自慢の農産物です。これら2つを使っていることは、PRポイントにもなります。

 地域資源活用分会のみなさんで、試行錯誤して完成させた漬け物の評判はどうでしたか。
地域資源活用分会のみなさんで、試行錯誤して完成させた漬け物の評判はどうでしたか。
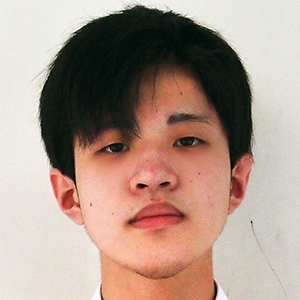 「更別村原産金時豆を使った白菜とスモモの甘酢漬け」と名付け、「漬物グランプリ2024」に応募したところ、学生の部75作品中、準グランプリを受賞しました。最終プレゼンでは、規格外の農産物を使い、環境に配慮した漬け物であることをアピールしました。
「更別村原産金時豆を使った白菜とスモモの甘酢漬け」と名付け、「漬物グランプリ2024」に応募したところ、学生の部75作品中、準グランプリを受賞しました。最終プレゼンでは、規格外の農産物を使い、環境に配慮した漬け物であることをアピールしました。
 金時豆ビネガーの製造技術は、「令和6年度 パテントコンテスト」に応募しました。ここでは、645件の応募の中から30件の優秀賞に選ばれるとともに、優れた技術であることが評価され、特許出願書類を提出するなど、高い評価を得ることができました。
金時豆ビネガーの製造技術は、「令和6年度 パテントコンテスト」に応募しました。ここでは、645件の応募の中から30件の優秀賞に選ばれるとともに、優れた技術であることが評価され、特許出願書類を提出するなど、高い評価を得ることができました。

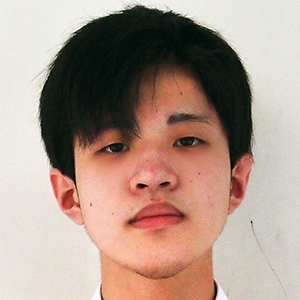 このような評価をいただけたのは、私たちだけの力ではありません。顧問の菊池先生がおっしゃったように、先輩方が10年間、継続して取り組んできた足跡があるからで、そのことを忘れてはいけないと感じています。
このような評価をいただけたのは、私たちだけの力ではありません。顧問の菊池先生がおっしゃったように、先輩方が10年間、継続して取り組んできた足跡があるからで、そのことを忘れてはいけないと感じています。
 研究目標には、「環境ビジネスとして成功させる」という柱もあったそうですね。
研究目標には、「環境ビジネスとして成功させる」という柱もあったそうですね。
 はい。どんなに素晴らしい研究でも、利益が出なければ、生産者の皆さんにご迷惑をおかけしてしまいます。ビジネスとして成功させるためにはどうしたらいいかを常に考えながら研究を進めていきました。
はい。どんなに素晴らしい研究でも、利益が出なければ、生産者の皆さんにご迷惑をおかけしてしまいます。ビジネスとして成功させるためにはどうしたらいいかを常に考えながら研究を進めていきました。
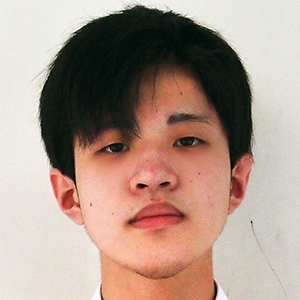 今後は、規格外野菜を活用したことを前面に押し出して販売することも、一つの方法だと感じました。
今後は、規格外野菜を活用したことを前面に押し出して販売することも、一つの方法だと感じました。
 お二人は地域資源活用分会の代表として、「MIRAI万博」でこの研究について発表しました。貴重な経験ですね。
お二人は地域資源活用分会の代表として、「MIRAI万博」でこの研究について発表しました。貴重な経験ですね。
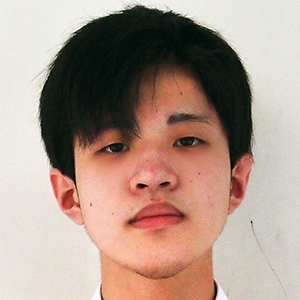 研究を続けてきてくれた先輩方のおかげです。先輩方には感謝しかありません。
研究を続けてきてくれた先輩方のおかげです。先輩方には感謝しかありません。
 二度とはない機会でした。さまざまな人が来場する会場で、発表することを楽しめました。
二度とはない機会でした。さまざまな人が来場する会場で、発表することを楽しめました。
 今後、どのような点を磨いていけば、北海道農業の可能性が広がっていくと思いますか。
今後、どのような点を磨いていけば、北海道農業の可能性が広がっていくと思いますか。
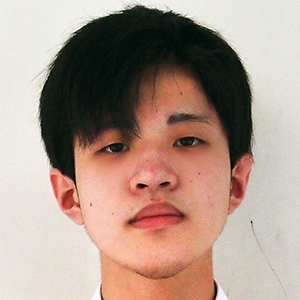 今回は、金時豆と白菜のみでしたが、他の規格外野菜も活用をめざしていくと良いのではないでしょうか。
今回は、金時豆と白菜のみでしたが、他の規格外野菜も活用をめざしていくと良いのではないでしょうか。
 私も同じ意見です。おいしく活用できることをPRすることが大切だと思います。
私も同じ意見です。おいしく活用できることをPRすることが大切だと思います。
 今後の活躍を楽しみにしています。今日はありがとうございました。
今後の活躍を楽しみにしています。今日はありがとうございました。