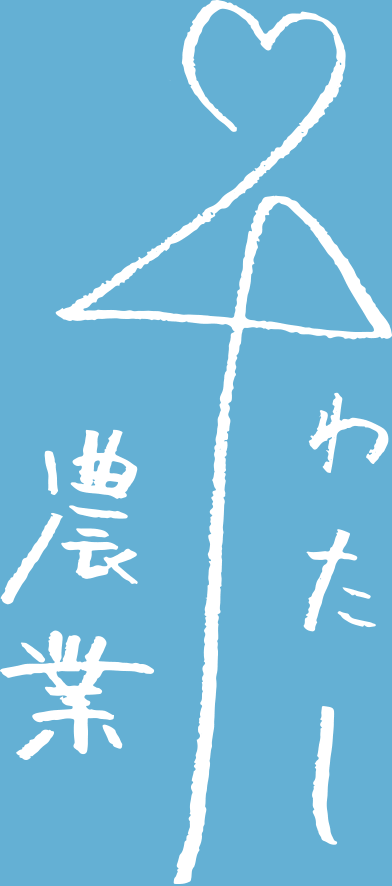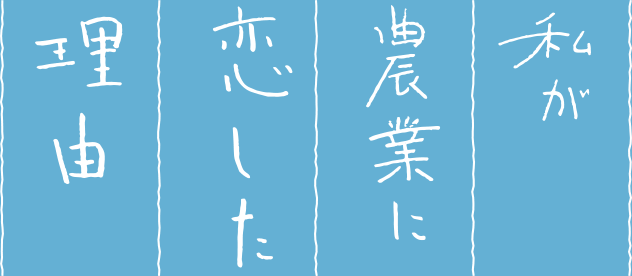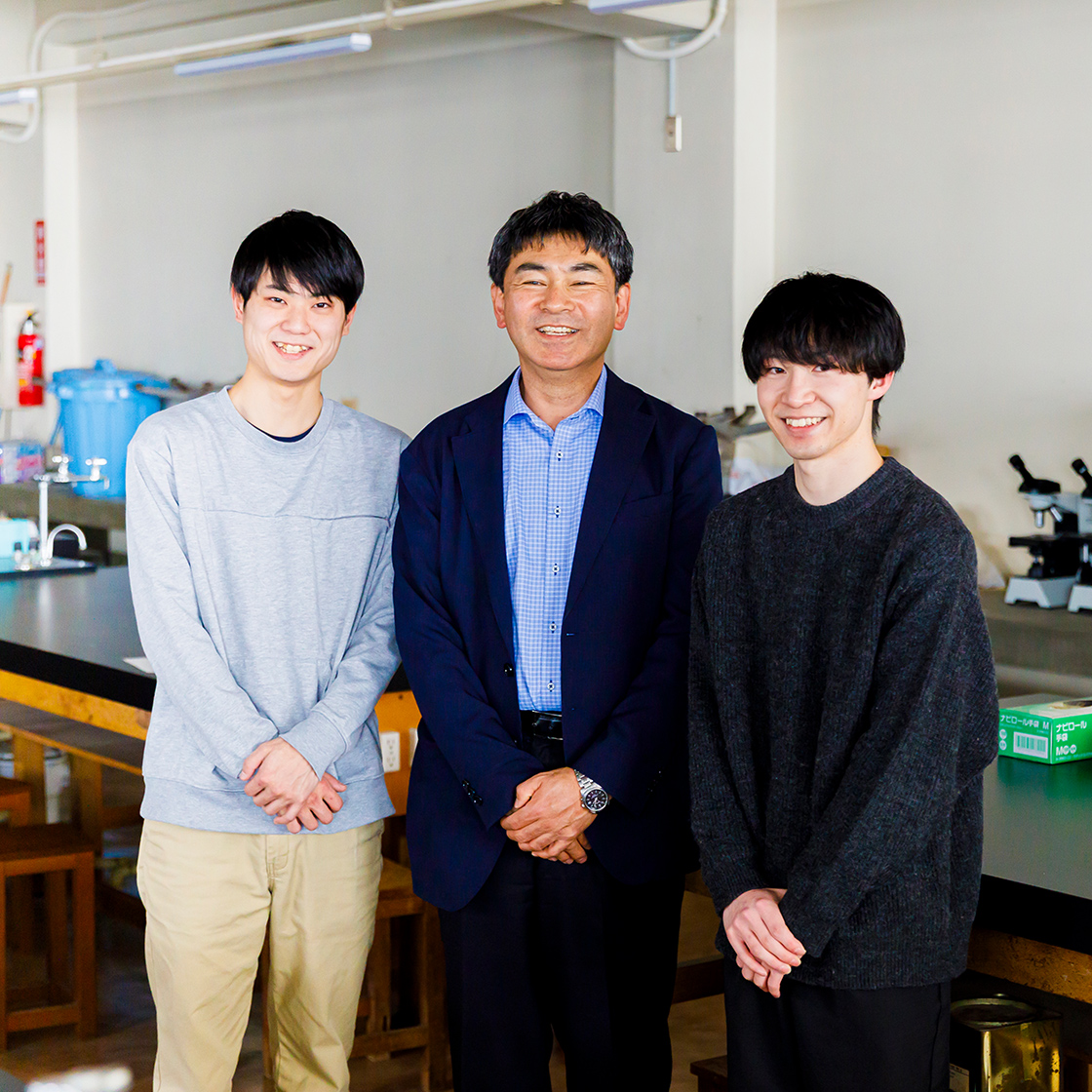今回は、酪農学園大学で豚の飼養管理技術を学ぶ4年生のお二人です。はじめまして。まず、酪農学園大学で学ぼうと思った理由から聞かせてください。
今回は、酪農学園大学で豚の飼養管理技術を学ぶ4年生のお二人です。はじめまして。まず、酪農学園大学で学ぼうと思った理由から聞かせてください。

 大学進学前から、将来は動物に携われる職業に就きたいと、動物園、畜産や酪農の現場をみてきました。そのうちに畜産、酪農に興味がしぼられ、現場に入って学べる場を求めて、酪農学園大学に進みました。僕は千葉県出身なのですが、高校生の頃に北海道で見た肉牛の放牧風景がずっと頭に残っていて、北海道で学べたらという気持ちもありました。
大学進学前から、将来は動物に携われる職業に就きたいと、動物園、畜産や酪農の現場をみてきました。そのうちに畜産、酪農に興味がしぼられ、現場に入って学べる場を求めて、酪農学園大学に進みました。僕は千葉県出身なのですが、高校生の頃に北海道で見た肉牛の放牧風景がずっと頭に残っていて、北海道で学べたらという気持ちもありました。
 僕は北見市育ち、帯広農業高校出身です。酪農に関わりたくて、農業高校を選びました。校内で育てている豚を初めて見たとき、そのかわいらしさに心を奪われ、豚を専門に学ぼうと決めました。下の写真は、大学で育てている子豚なんですが、かわいいと思いませんか? 大学選びでは、エコフィード(食品製造副産物等を利用して製造された飼料)の研究も進んでいる酪農学園なら、豚の飼養とエコフィードを並行して学べる点が決め手になりました。
僕は北見市育ち、帯広農業高校出身です。酪農に関わりたくて、農業高校を選びました。校内で育てている豚を初めて見たとき、そのかわいらしさに心を奪われ、豚を専門に学ぼうと決めました。下の写真は、大学で育てている子豚なんですが、かわいいと思いませんか? 大学選びでは、エコフィード(食品製造副産物等を利用して製造された飼料)の研究も進んでいる酪農学園なら、豚の飼養とエコフィードを並行して学べる点が決め手になりました。

 お二人は、豚をはじめとする中小家畜の飼養管理そしてエコフィードの活用を専門に研究されている山田未知教授の研究室に所属しているそうですね。山田教授、エコフィードを活用することの効用について、ご意見を聞かせていただけますか。
お二人は、豚をはじめとする中小家畜の飼養管理そしてエコフィードの活用を専門に研究されている山田未知教授の研究室に所属しているそうですね。山田教授、エコフィードを活用することの効用について、ご意見を聞かせていただけますか。
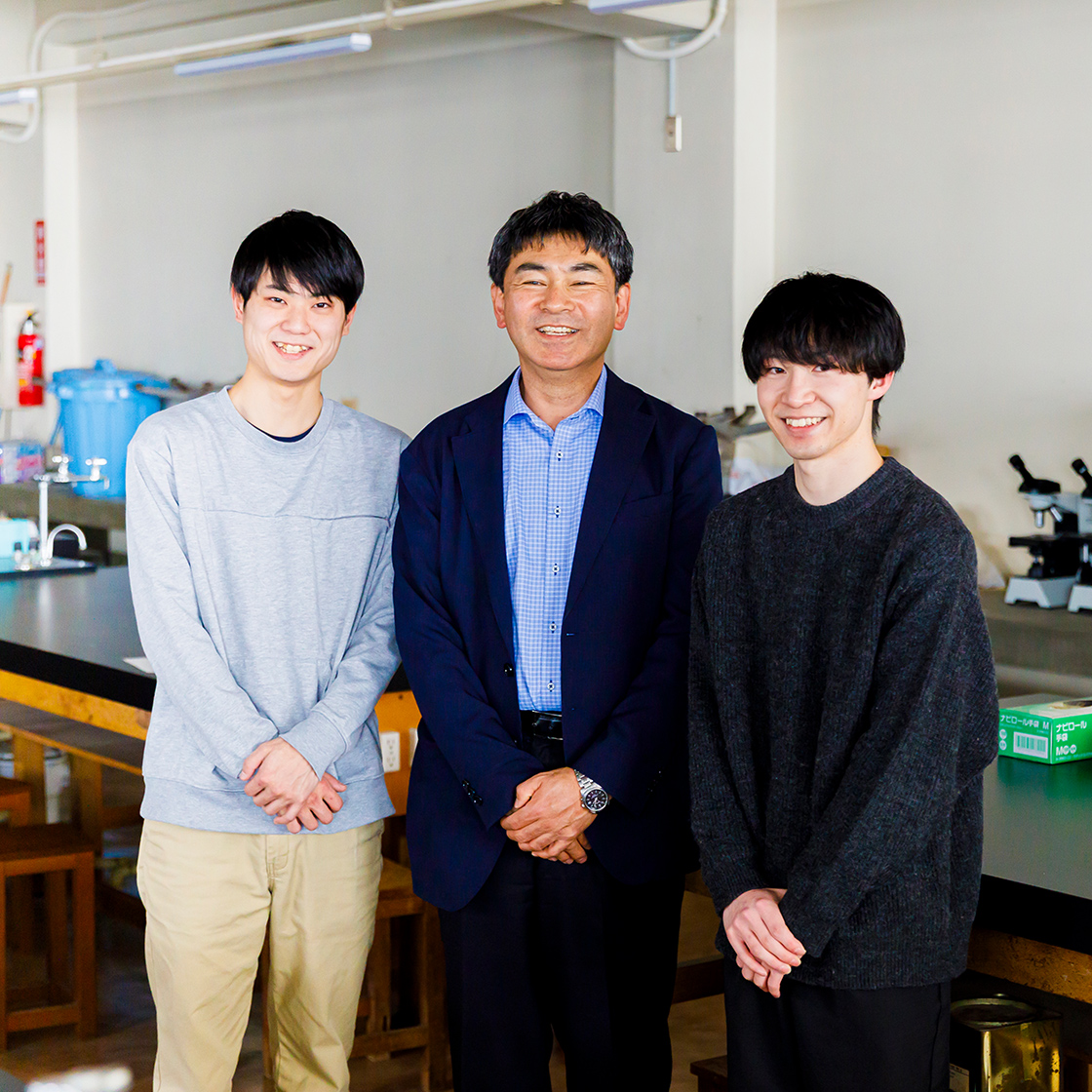
 使い切れていない有機物をうまく活用して、農畜産物を循環資源利用体系の中で生産できる仕組みは、北海道にこそ必要で、そのひとつとしてエコフィードが有効だと考えています。食品残渣(さ)などの有機物を循環させ、農業に生かす取り組みに挑戦するには、ある程度のスケール感が必要であり、トライしたくてもできない他府県もあるなか、北海道なら可能です。北海道農業は、循環型社会を担えるという確信をもって、研究に臨んでいます。
使い切れていない有機物をうまく活用して、農畜産物を循環資源利用体系の中で生産できる仕組みは、北海道にこそ必要で、そのひとつとしてエコフィードが有効だと考えています。食品残渣(さ)などの有機物を循環させ、農業に生かす取り組みに挑戦するには、ある程度のスケール感が必要であり、トライしたくてもできない他府県もあるなか、北海道なら可能です。北海道農業は、循環型社会を担えるという確信をもって、研究に臨んでいます。

 現実的で、可能性の広がりが感じられる研究ですね。お二人は、山田教授の研究室でどのような取り組みをしてきたのですか。
現実的で、可能性の広がりが感じられる研究ですね。お二人は、山田教授の研究室でどのような取り組みをしてきたのですか。
 日本では、母豚を個別に柵で囲うストール飼育が多いのですが、大学では昼間は複数の母豚を放牧しています。僕は動物の行動を見ることも好きなので、ストール飼育から昼間に放牧する飼育に変えると、どのような変化があるかを研究することにしました。
日本では、母豚を個別に柵で囲うストール飼育が多いのですが、大学では昼間は複数の母豚を放牧しています。僕は動物の行動を見ることも好きなので、ストール飼育から昼間に放牧する飼育に変えると、どのような変化があるかを研究することにしました。

 その変化は、どのような指標を用いて調べるのですか。
その変化は、どのような指標を用いて調べるのですか。
 ストレス指標となる物質の増減をみるんです。ストール飼育していた母豚を放牧に出すと、ストレスが一旦高まりますが、群れのなかでボスが決まっていくなどすると、ストール飼育と同程度にまで落ち着きます。また、放牧すると、穴掘りや泥浴びをするなど、豚の習性である行動を起こすようになります。当然ながら、ストール飼育は個体管理がしやすく、管理する人間にとってはメリットがあります。ストール飼育と放牧、それぞれのいいとこどりをした方法を見出せたらと、いまも考えています。
ストレス指標となる物質の増減をみるんです。ストール飼育していた母豚を放牧に出すと、ストレスが一旦高まりますが、群れのなかでボスが決まっていくなどすると、ストール飼育と同程度にまで落ち着きます。また、放牧すると、穴掘りや泥浴びをするなど、豚の習性である行動を起こすようになります。当然ながら、ストール飼育は個体管理がしやすく、管理する人間にとってはメリットがあります。ストール飼育と放牧、それぞれのいいとこどりをした方法を見出せたらと、いまも考えています。

 三宅さんは、どのような研究をしてきましたか。
三宅さんは、どのような研究をしてきましたか。
 1カ月後の豚の発育を予測するにはどうしたらいいのかをテーマにしました。僕は、約1年間農場に入り、大きな豚を出荷するまでの肥育後期を担当しました。出荷にあたっては、事前に取引先様に出荷可能な頭数を伝えなければならず、そのために、一頭一頭の体重を測定し、さらに1カ月後の体重を予測することになります。体重は気温の変化などにも影響を受けますし、一度に100頭規模を出荷する大規模な養豚会社もあります。そこで僕は、出荷計画の精度をあげようと、豚の性別、品種、体重、気温をベースに1カ月後の体重の予測式を考案しました。
1カ月後の豚の発育を予測するにはどうしたらいいのかをテーマにしました。僕は、約1年間農場に入り、大きな豚を出荷するまでの肥育後期を担当しました。出荷にあたっては、事前に取引先様に出荷可能な頭数を伝えなければならず、そのために、一頭一頭の体重を測定し、さらに1カ月後の体重を予測することになります。体重は気温の変化などにも影響を受けますし、一度に100頭規模を出荷する大規模な養豚会社もあります。そこで僕は、出荷計画の精度をあげようと、豚の性別、品種、体重、気温をベースに1カ月後の体重の予測式を考案しました。

 お二人とも現場を知っているからこそ得られた、研究テーマですね。この研究内容を3月26日(水)に神奈川県で開催される日本養豚学会の大会で発表されるそうですね。
お二人とも現場を知っているからこそ得られた、研究テーマですね。この研究内容を3月26日(水)に神奈川県で開催される日本養豚学会の大会で発表されるそうですね。
 はい。僕の題は、「ストール飼育と昼間放牧群飼育を組み合わせた飼養形態が繁殖雌豚の行動とストレス指標物質に及ぼす影響」です。
はい。僕の題は、「ストール飼育と昼間放牧群飼育を組み合わせた飼養形態が繁殖雌豚の行動とストレス指標物質に及ぼす影響」です。

 僕は、「発育に関わる要因の組み合わせを活用した肥育豚の適正出荷日齢予測の試み」です。それぞれ、一緒に研究を進めたメンバーと山田教授とチームで発表します。
僕は、「発育に関わる要因の組み合わせを活用した肥育豚の適正出荷日齢予測の試み」です。それぞれ、一緒に研究を進めたメンバーと山田教授とチームで発表します。

 大学生活をしめくくる大舞台ですね。卒業後、お二人は就職されるのですか?
大学生活をしめくくる大舞台ですね。卒業後、お二人は就職されるのですか?

 僕は、豚舎システムの設計・施工や養豚器具の製造・販売を行う会社に就職します。大学で学んだことを生かして、養豚会社の経営者をサポートしていきます。
僕は、豚舎システムの設計・施工や養豚器具の製造・販売を行う会社に就職します。大学で学んだことを生かして、養豚会社の経営者をサポートしていきます。
 豚の飼育・加工・販売企業に就職します。飼育では、繁殖から肥育まで一貫生産にこだわっている会社ですから、受胎率が下がりがちな夏でも、繁殖に悪影響が出ないような取り組みを提案していきたいと考えています。
豚の飼育・加工・販売企業に就職します。飼育では、繁殖から肥育まで一貫生産にこだわっている会社ですから、受胎率が下がりがちな夏でも、繁殖に悪影響が出ないような取り組みを提案していきたいと考えています。
 東さんは現場、三宅さんは現場のサポートの仕事ですね。お二人が組んだら、養豚業界に新風を巻き起こせそうです。そんなお二人から、最後に消費者の方々や同世代にメッセージをお願いします。
東さんは現場、三宅さんは現場のサポートの仕事ですね。お二人が組んだら、養豚業界に新風を巻き起こせそうです。そんなお二人から、最後に消費者の方々や同世代にメッセージをお願いします。
 物価高が続いていますが、国産のものを消費してもらえるとありがたいです。もっと言えば、各地にその土地のブランド豚があると思いますので、ぜひ召し上がってみてほしいですね。
物価高が続いていますが、国産のものを消費してもらえるとありがたいです。もっと言えば、各地にその土地のブランド豚があると思いますので、ぜひ召し上がってみてほしいですね。
 同世代には、第一次産業にもっと関心を寄せてほしいですし、第一次産業にもっと入ってほしいです。
同世代には、第一次産業にもっと関心を寄せてほしいですし、第一次産業にもっと入ってほしいです。
 農業の醍醐味や可能性の一端にふれられるお話をありがとうございました。今後のご活躍に期待しています。
農業の醍醐味や可能性の一端にふれられるお話をありがとうございました。今後のご活躍に期待しています。