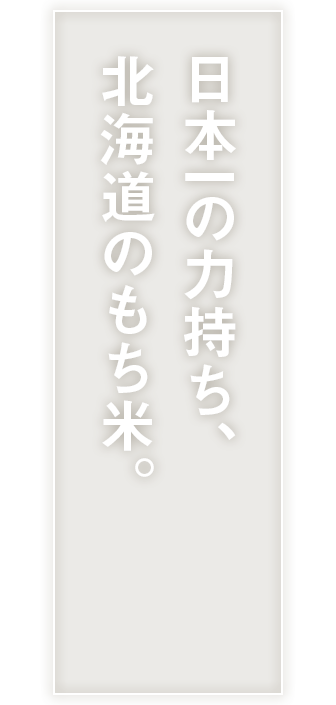
「北限の地で取り組んだ努力も、日本一だと思います」


もち米作りは水加減が肝心
私たちが向かったのは、作付面積と生産量で日本一を誇るもち米の産地、名寄市。北海道のほぼ中央の旭川市から、さらに車で1時間半ほど北上した位置にあります。出迎えてくれたのは、JA道北なよろのもち米生産者組織「名寄市もち米生産組合」の組合長を務める、及川友和さん。及川さんは「なよろ名誉もち大使」の肩書きも持ち、産地の“顔”として活躍する人物でもあります。
就農時からもち米を育てる及川さんの栽培歴は、実に24年。両親からもち米作りのイロハを学び、現在は約15haもの面積にもち米を作付しています。
「もち米作りで気を配る作業はいくつもありますが、一つあげるとするならば水管理ですね。昔から“米作り、飯になるまで水加減”といわれているほど、田んぼに張る水の量は、稲の出来に大きく影響します。生育状態や気温にも左右されるため、正解はありません」
及川さんによると、田んぼに植えたばかりの稲は特に寒さに弱いため、水を深く張り低温から稲を守るといいます。「ただし、深水にし過ぎると生育が進みにくくなるので、あまり深水にしたくないという思いもあります。それでも例年6月下旬から7月中旬ぐらいまでに寒さにあたると、その後の生育に影響し、減収にもつながってしまうので非常に気を使います」。
-

名寄市ではこの夏、30度を超える日が14日間も続いたそうです。そのため「例年よりも、10日から一週間ほど収穫が早まっています」と及川さん。明日にでも収穫できそうな、たわわに実った稲穂(取材:2021年9月中旬)
抜き穂作業で品質を守る
一般的にもち米の栽培方法は、うるち米とほぼ同じです。しかしもち米ならではといえるのが、例年8月下旬頃に行う〝抜き穂〟と呼ばれる作業。もち米にはうるち米を掛け合わせて作られている品種があるため、ごくまれにうるち米が生えてくることがあると及川さんは説明します。
「〝先祖返り〟したうるち米は、うちの田んぼで例年1株、2株あるかどうかです。それでも見逃すわけにはいかないので、すべての田んぼを見回って、変異株を株ごと抜き取ります」
その判別方法は、主に目視。「よく見ると、うるち米はもち米よりも毛がふさふさしていて、穂も長いんです。念のため抜き取った籾をヨードチンキで判定すると、うるち米は赤い液が黒っぽい紫色に変わります」。
毎年徹底して取り除くのは、うるち米が混入してしまうと、加工の際に品質が落ちてしまうという理由から。「良質なもち米を届ける意味でも、決して怠ってはならないんです」と及川さんは力説します。
現在、及川さんが目指しているのは、新しい技術を取り入れて、生産性を向上させるもち米作りです。
「やりがいを感じるのは、やっぱりたくさんもち米がとれた時。そのために農作業を頑張って、毎年勉強もして、収量アップにつながりそうなことは、一つ一つ試すようにしています」
その際の情報源となるのが、仲間の存在です。「ここはもち米団地なので、周りはもち米の田んぼだらけなんです。道を通るたびに、〝ここの家は、めちゃくちゃ生育がいいなあ〟〝あの家の稲はすごいぞ〟と、どうしても目が向きます(笑)。そこで、どんな資材を使って、どのように育てているのか生産者に話を聞き、同じ方法を取り入れるようにしています」。毎年組合による苗の生育調査や抜き穂の徹底、収穫適期の判定を実施し、組合長として、産地全体の品質向上にも取り組んでいます。
「かつては稲作の北限といわれ、辛酸をなめてきた先人の苦労があって今があります。その努力も日本一だと思っています」
-

「どこの家も、いいもち米を作っていますが、自分が作ったもち米は負けていないと思っています」と及川さん
- 『もち米』生産者 及川 友和さん[JA道北なよろ]
名寄市出身。北海道立農業大学校卒業後、1997年に就農。現在はもち米(はくちょうもち、風の子もち)をメインに、大豆、小麦、スイートコーン、長いもを栽培。2020年に「名寄市もち米生産組合」の組合長に就任。

