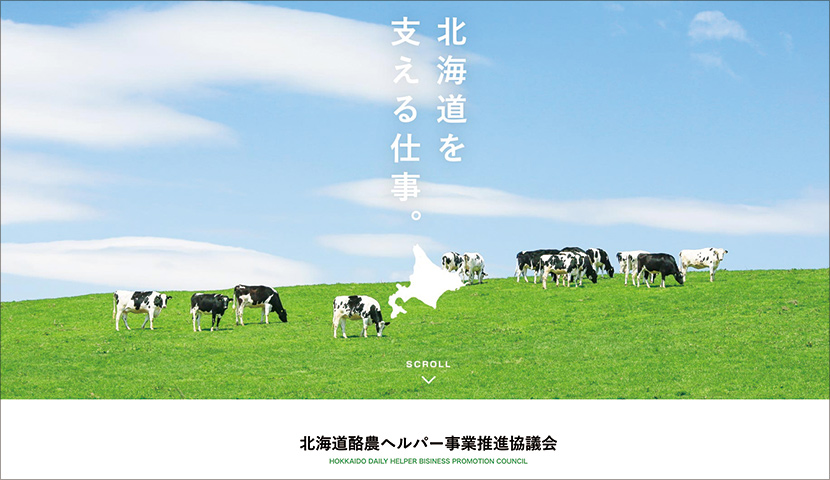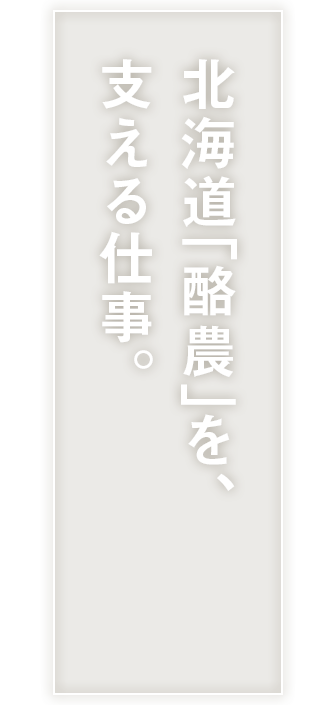
酪農ヘルパー/北海道「酪農」を、支える仕事。
ヘルパーが増え、誰もが休める酪農になることが理想です


北海道酪農ヘルパー事業推進協議会 会長 熊谷 康浩さん
浜中町出身。1986年に酪農家の三代目として就農。2018年『株式会社熊谷牧場』の代表に就任。現在は、約600頭の乳用牛を飼育。2019年より現職。『有限会社浜中町酪農ヘルパー組合』の代表取締役も務める。
助っ人という名の酪農専門の職業
皆さんは、「酪農ヘルパー」をご存じですか? 名称は聞いたことがあっても、どういう仕事なのかよく分からない……という人も多いかもしれません。
酪農家は生き物を相手にしているため、365日、世話を欠かすことができません。そこで活躍するのが、酪農ヘルパーです。年中無休で働く酪農家の代わりに、給餌や搾乳など牛の世話をするのが酪農ヘルパーの役割です。
「〝ヘルパー〟と聞くと、アルバイトやパートと捉えがちですが、れっきとした職業です。実際は各地域にあるヘルパー組織の職員という位置づけで、福利厚生も整っています」
このように説明するのは、道内86の酪農ヘルパー利用組織を束ねる「北海道酪農ヘルパー事業推進協議会」会長の熊谷康浩さん。酪農家でありながら、地元の酪農ヘルパー組合の代表も務めています。
酪農ヘルパーには、「動物に関わる仕事がしたい」という動機で働いている人や、自ら酪農を始めるためのステップとして、酪農ヘルパーになる人も多くいます。
「酪農家は、基本的に乳を搾って出荷するという目的は同じですが、飼育方法や給餌・搾乳の時間などは家ごとに異なります。1カ所にとどまらず、複数の牧場で働く酪農ヘルパーには、あらゆる飼育方法や経営について学べるという利点もあります」
ヘルパー職員の人材不足が課題
酪農ヘルパー制度は、酪農経営の安定的な発展のために酪農家の休日を確保し、心身の休養や、酪農家とその家族の病気や事故、冠婚葬祭などに対処することを目的に、全国で事業化されました。
「酪農家にも休みは必要で、リフレッシュできると仕事へのモチベーションが高まります。それが心身の健康や、農作業の安全にも関わってくると感じています」
北海道では近年、酪農家の離農が増加傾向にあります。その一方、規模拡大で飼養頭数を増やし、生乳の増産を目指す酪農家も多くいます。
「搾乳ロボットなど酪農も機械化が進んでいますが、機械を動かすにも管理をするにも、人の力は必要です。また、酪農家はひとたび病気やけがをしてしまうと、経営が成り立たなくなってしまいます。だからこそヘルパーは、酪農家にとって、なくてはならない存在なんです」
実際に、北海道における酪農ヘルパーへの需要は年々増えており、ヘルパーの利用日数も増加しています。しかし一方で、道内約5千戸の酪農家に対して、ヘルパーの登録者は700人程度と、ヘルパーの人材不足が大きな課題となっています。そこで同協議会では、ヘルパー職員の確保を目的に、道内外の農業系大学を中心に、インターンシップの受け入れに力を入れています。
-

酪農ヘルパーの作業風景
「私たちの地域でもヘルパー職員不足で、酪農家から申し込みがあっても、3割ほどは断らざるを得ない状況です。皆さんの要望に応えられるように、できる限りの努力は続けたいです」と熊谷さん
「酪農に興味を持ってもらうには、実際に体験してもらうことが一番です。大学を訪問すると、男性はもちろん、多くの女性が参加を希望してくれます」
加えて、職員のケアにも重点を置き、一人ひとりの意見や要望に耳を傾けて、長期雇用の維持にも取り組んでいます。
「酪農家さんに直接言いにくいことは、私たちから労働環境の改善を働きかけます。その上で職員には、酪農家の財産を扱っているという責任を持って作業してほしいと伝えています」
熊谷さんは、酪農家が安心して任せられるヘルパーが増えることで、誰もが働きやすい酪農になることが理想だと考えています。
「私が子どもの頃は、親と一緒に旅行した思い出はありません。自分の代で、子どもたちと旅行に出かけることができました。なくしてはならないこの事業に力を尽くして、次の世代につなげていきたいです」と力強く語りました。