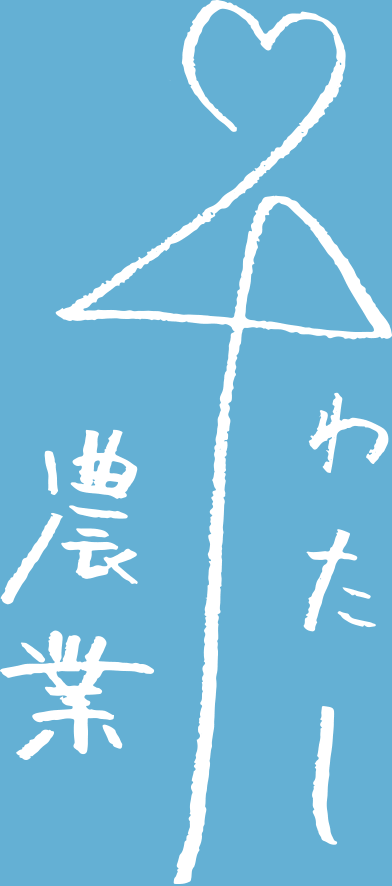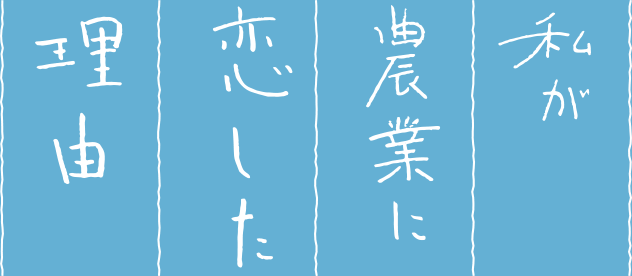2022年1月、美幌高校が道内初の高校生による会社、「合同会社アグリロテート(以下、アグリロテート)」を設立し、新岡さんは初代社長に就任しました。おめでとうございます。さっそくですが、会社設立のきっかけを教えてください。
2022年1月、美幌高校が道内初の高校生による会社、「合同会社アグリロテート(以下、アグリロテート)」を設立し、新岡さんは初代社長に就任しました。おめでとうございます。さっそくですが、会社設立のきっかけを教えてください。
 はじめまして。よろしくお願いします。成り立ちとしては、私も所属している美幌高校の「農業クラブ アグリビジネス専門部」が全国農業協同組合中央会・毎日新聞社主催「第5回全国高校生農業アクション大賞」に応募し、3年間の支援対象認定グループに選ばれたことが発端です。その際に授与された活動支援金20万円をもとに、アグリロテートを設立しました。
はじめまして。よろしくお願いします。成り立ちとしては、私も所属している美幌高校の「農業クラブ アグリビジネス専門部」が全国農業協同組合中央会・毎日新聞社主催「第5回全国高校生農業アクション大賞」に応募し、3年間の支援対象認定グループに選ばれたことが発端です。その際に授与された活動支援金20万円をもとに、アグリロテートを設立しました。
 そもそも、美幌高校自体にチャレンジする土壌があるように感じますが、学びの特徴があるのでしょうか。
そもそも、美幌高校自体にチャレンジする土壌があるように感じますが、学びの特徴があるのでしょうか。
 美幌高校では、一人一ほ場制度による「農産物の生産や販売」、一人一商品開発制度のような「商品開発や販売」などの実習があります。校内にある「びほろ農場」には、写真の動物舎実習棟をはじめ、実習ほ場、食品製造・加工実習棟、園芸用ガラス温室などがあり、実践的な学びの場になっています。
美幌高校では、一人一ほ場制度による「農産物の生産や販売」、一人一商品開発制度のような「商品開発や販売」などの実習があります。校内にある「びほろ農場」には、写真の動物舎実習棟をはじめ、実習ほ場、食品製造・加工実習棟、園芸用ガラス温室などがあり、実践的な学びの場になっています。

 アグリビジネス専門部から会社が生まれた経緯も知りたいです。
アグリビジネス専門部から会社が生まれた経緯も知りたいです。
 アグリビジネス専門部は、顧問の三浦先生のもとで、地域にある資源を再確認し、どのようにしたら利益が出るのか、人を呼び込めるか、あわせて効率的な流通などを考え、学んでいます。多角的な学びを積み重ねていくうちに、高校での模擬的な枠組みを超えてみたいという気持ちが自然と湧き、会社設立につながっていきました。また、三浦先生は、「美幌高校のように、地域にひとつしかない高校は、将来の地域経済の担い手の育成が責務」とお考えで、アグリロテートという枠組みが私たち生徒の可能性を広げるきっかけになると期待してくださっています。
アグリビジネス専門部は、顧問の三浦先生のもとで、地域にある資源を再確認し、どのようにしたら利益が出るのか、人を呼び込めるか、あわせて効率的な流通などを考え、学んでいます。多角的な学びを積み重ねていくうちに、高校での模擬的な枠組みを超えてみたいという気持ちが自然と湧き、会社設立につながっていきました。また、三浦先生は、「美幌高校のように、地域にひとつしかない高校は、将来の地域経済の担い手の育成が責務」とお考えで、アグリロテートという枠組みが私たち生徒の可能性を広げるきっかけになると期待してくださっています。

 社名の由来と、会社が掲げる目的を聞かせてください。
社名の由来と、会社が掲げる目的を聞かせてください。
 社名は「アグリ(農業)」と「ロテート(循環する)」に由来し、高校生が創り出した事業が世界を巻き込んだ企業に発展していく願いをこめています。美幌町には肥沃で広大な農地があり、そこでは主要作物のビート(てん菜)、ばれいしょ、小麦が生産されています。こうした特性をいかし、消費づくりや自然を生かした体験を提供する活動を考え、販売することが私たちの目的です。
社名は「アグリ(農業)」と「ロテート(循環する)」に由来し、高校生が創り出した事業が世界を巻き込んだ企業に発展していく願いをこめています。美幌町には肥沃で広大な農地があり、そこでは主要作物のビート(てん菜)、ばれいしょ、小麦が生産されています。こうした特性をいかし、消費づくりや自然を生かした体験を提供する活動を考え、販売することが私たちの目的です。

 主な事業内容について説明してもらえますか。
主な事業内容について説明してもらえますか。
 地域農業の課題解決と、農業生産に貢献できる事業として、最初に掲げているのは、「農業を含む第一次産業が連携できるプラットホームを構築し、食料生産の効率化や地域産業の強靭化を図ること」です。地域にある農林水産業が経営資材や所有財産などを共有化することで、経済的で効率のよい生産ができるような枠組み、もしくは仕組みを作りたいです。
地域農業の課題解決と、農業生産に貢献できる事業として、最初に掲げているのは、「農業を含む第一次産業が連携できるプラットホームを構築し、食料生産の効率化や地域産業の強靭化を図ること」です。地域にある農林水産業が経営資材や所有財産などを共有化することで、経済的で効率のよい生産ができるような枠組み、もしくは仕組みを作りたいです。

 その他の事業についても教えてください。
その他の事業についても教えてください。
 校内の演習林など荒廃した林野を整備し、育林を行い、あわせて伐り倒した材木から薪を生産し、販売します。アグリロテートで販売予定の薪は、試作を始めています。
校内の演習林など荒廃した林野を整備し、育林を行い、あわせて伐り倒した材木から薪を生産し、販売します。アグリロテートで販売予定の薪は、試作を始めています。

 仕事が着々と進んでいますね。
仕事が着々と進んでいますね。
 はい。このほか、堆肥を用いた循環型農業生産から豊かな土壌環境を創り、生産物の販売も手掛けたいですし、試食会や体験会など企画型グリーンツーリズムの販売も視野に入れています。そのひとつとして寒中焼肉を企画していて、下の写真は先生が獲ってきたエゾシカでジンギスカンを試しているところです。最終的な目標は、一次産業全体が「笑顔になる」ような継続企業を作りだすことです。
はい。このほか、堆肥を用いた循環型農業生産から豊かな土壌環境を創り、生産物の販売も手掛けたいですし、試食会や体験会など企画型グリーンツーリズムの販売も視野に入れています。そのひとつとして寒中焼肉を企画していて、下の写真は先生が獲ってきたエゾシカでジンギスカンを試しているところです。最終的な目標は、一次産業全体が「笑顔になる」ような継続企業を作りだすことです。

 地域を育てていく会社ですね。ところで、社長という大役を担うにあたって、迷いはありませんでしたか。
地域を育てていく会社ですね。ところで、社長という大役を担うにあたって、迷いはありませんでしたか。
 正直、社長になると決まった時、その立場でやっていくことができるか不安でした。しかし、やると決めた以上、最後までやり切ろうと決意しました。
正直、社長になると決まった時、その立場でやっていくことができるか不安でした。しかし、やると決めた以上、最後までやり切ろうと決意しました。
 会社設立までに、大変な思いをしたこともあったのではないですか。
会社設立までに、大変な思いをしたこともあったのではないですか。
 昨年11月に法人登記を済ませたのですが、定款を作成する中で事業内容をまとめていくところが大変で、公認会計士や税理士の方々から助言をいただきました。また、今回の設立をきっかけに金融機関から、金融に関する講義を受けられるようにもなり、感謝しています。
昨年11月に法人登記を済ませたのですが、定款を作成する中で事業内容をまとめていくところが大変で、公認会計士や税理士の方々から助言をいただきました。また、今回の設立をきっかけに金融機関から、金融に関する講義を受けられるようにもなり、感謝しています。

 社員は何名ですか。
社員は何名ですか。
 アグリビジネス専門部に所属する1~3年生の計11名で、全員が販売課長や事業課長、広報課長などの肩書を持って活動しています。また、美幌高校農業クラブOBで美幌商工会議所の横山清美専務が代表社員に名を連ねています。
アグリビジネス専門部に所属する1~3年生の計11名で、全員が販売課長や事業課長、広報課長などの肩書を持って活動しています。また、美幌高校農業クラブOBで美幌商工会議所の横山清美専務が代表社員に名を連ねています。

 高校生ではなく、会社員として動くことで、どのような可能性や変化が生まれそうですか。
高校生ではなく、会社員として動くことで、どのような可能性や変化が生まれそうですか。
 自分たちのアイデアから商品や体験を考え、会社を経営していくことで、自分たちの新たな力の発見や農業の新たな形をみつけることができると思っています。
自分たちのアイデアから商品や体験を考え、会社を経営していくことで、自分たちの新たな力の発見や農業の新たな形をみつけることができると思っています。
 先駆的な取り組みは、大人にも地域にも刺激になっています。今後の活躍を期待しています。ありがとうございました。
先駆的な取り組みは、大人にも地域にも刺激になっています。今後の活躍を期待しています。ありがとうございました。