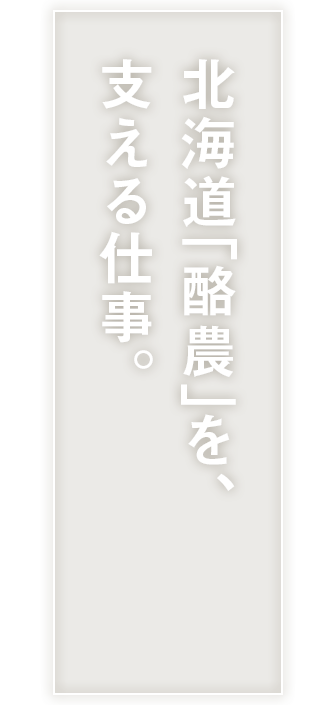
牛削蹄師/北海道「酪農」を、支える仕事。
蹄を見ると、牛の健康状態がある程度分かります


有限会社 久津間装蹄所
北海道の道央圏を中心に、牛の削蹄を行う。年間に削蹄する牛の頭数は1万8000頭以上に上る。
北海道の酪農を足元から支える職人
乳用牛や肉用牛の蹄(爪)を削り、整える「牛削蹄師」。
蹄が伸びてしまった牛は姿勢が崩れ、ストレスがたまり、さまざまな病気にかかりやすくなります。それは、乳が出なくなったり、繁殖率の低下を招く要因にもつながります。
そこで、牛削蹄師の出番です。酪農家の大切な牛を健康に長生きさせるため、蹄の手入れを行います。牛の蹄は「第2の心臓」とも呼ばれるほど重要な役割を担っており、削蹄師は日本の酪農の発展に、なくてはならない存在です。
牛の健康維持のため年に2〜3回削蹄
ひょいと牛の脚を脇に持ち抱え、ナタや鎌型の道具を持ち替えながら手際よく蹄を削っていく─。わずか10分ほどで牛一頭の蹄が見事に整いました。『有限会社 久津間装蹄所』代表で、日本装削蹄協会指導級認定牛削蹄師の久津間正登さんは「牛の機嫌を見ながら、安全に行うことが重要です。イライラしてくると奥歯を噛んだような顔で、目つきが悪くなっていきます。牛が飽きる前に、手早く済ませます」と笑顔を見せます。
近年は機械を使った削蹄も増えてきています。同社は、牛を固定する器具(枠場)を使わず、人の手で削蹄を行う昔ながらのスタイルに定評があります。
「人の手で削蹄する一番のメリットは、牛舎内でできることです。牛がいつもいる環境で削蹄でき、また手作業で行うことで大きな音も出ず、牛を怖がらせることもありません」
-

脚を上げるコツは「力を使わず、牛に上げてもらうこと。祖母に教えられました」と久津間さん。
700キロ前後ある牛の体重を支える蹄には、相当な負荷がかかります。蹄の長さや形を整えることは、牛の健康維持に欠かせません。乳用牛の場合は、年に2〜3回は削蹄するのが望ましいといいます。
「蹄の状態で、牛の健康状態もある程度分かります。血液の循環の良し悪しや、餌の栄養状態も蹄に現れます」と久津間さん。牧場主の中村諭さんは「牛の不調は足からくるので、削蹄は大事なケアです。久津間さんとは15年以上の付き合いで、私が気づけないことも教えてもらっています」と話します。
-

硬くなった蹄は、両手で使える大型の器具で粗く削り、小型の鎌で丁寧に仕上げます
人と同様に、牛の体形や蹄の形も一頭一頭異なります。東海林優さんと新知幸さんは、それぞれの牛に合わせて整えるのは難しく、けれどもそこが面白いと口を揃えます。
「牛の飼育方法によって削り方も変えています。つなぎ牛舎だと動き回らないので、古い角質をしっかり剥がしてあげます。牛が自由に歩ける牛舎では、角質を残し、靴下を履かせるようなイメージで仕上げています。整えた後の姿勢が明らかに変わると、やりがいを感じます」と東海林さん。
「指導級になってから、人に教える機会が増えました。削蹄は感覚的な判断が多いため、言葉で伝えるのに苦労しています。技術は続けることで身についていくものなので、一人でも長く続けてほしいです」と新さん。
3人は、酪農学園大学(江別市)で実施されている、二級認定牛削蹄試験の講師を6年前から務めています。「削蹄師の資格を取得する人や就職を志望する学生も増えて、お手伝いした結果が実りつつあると感じています」と久津間さん。後進も育っているようです。
-

最上位の、指導級認定牛削蹄師の資格を持つ3人。左から、新知幸さん、久津間正登さん、東海林優さん

