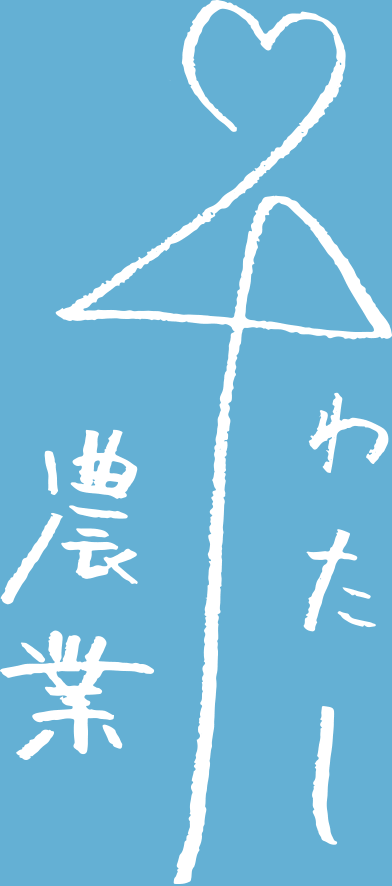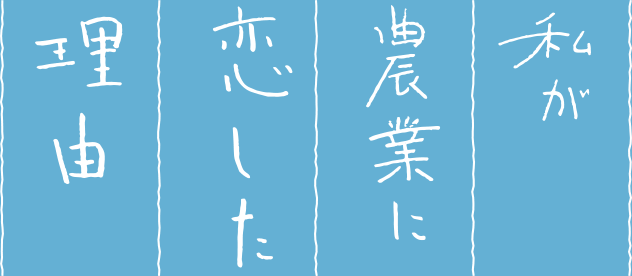谷本さん、こんにちは。新十津川町といえば、北海道でも有数の米どころ。その町にある農業高校で、稲作を熱心に学んでいるそうですね。ご実家も稲作を行っているんですか。
谷本さん、こんにちは。新十津川町といえば、北海道でも有数の米どころ。その町にある農業高校で、稲作を熱心に学んでいるそうですね。ご実家も稲作を行っているんですか。

 いいえ、実家は農家ではないんです。農業を営んでいるのは祖父と叔父で、私は叔父が作ったお米を食べて育ちました。子どもの頃から、祖父や叔父が働いている姿を見ては、「あんな風にかっこいい大人になりたい」と憧れていました。農家になりたいと、農業について深く勉強するようになったのは、高校2年の頃から。叔父のあとをつぐことができたらと考えています。
いいえ、実家は農家ではないんです。農業を営んでいるのは祖父と叔父で、私は叔父が作ったお米を食べて育ちました。子どもの頃から、祖父や叔父が働いている姿を見ては、「あんな風にかっこいい大人になりたい」と憧れていました。農家になりたいと、農業について深く勉強するようになったのは、高校2年の頃から。叔父のあとをつぐことができたらと考えています。
 叔父さんのお手伝いもよくするんですか。
叔父さんのお手伝いもよくするんですか。
 はい、今年は、コロナウイルス感染症の影響で学校が長期休校になったので、ハウスにビニールをかけるところから、田植え作業が終わるまで手伝いました。GPS付きのトラクターと田植え機で水田の耕起、田植え作業もやらせてもらえ、これからの農業スタイルを学ぶことができたと感謝しています。
はい、今年は、コロナウイルス感染症の影響で学校が長期休校になったので、ハウスにビニールをかけるところから、田植え作業が終わるまで手伝いました。GPS付きのトラクターと田植え機で水田の耕起、田植え作業もやらせてもらえ、これからの農業スタイルを学ぶことができたと感謝しています。
 叔父さんは、スマート農業を取り入れているんですね。新十津川農業高校でも、スマート農業の授業があるそうですね。
叔父さんは、スマート農業を取り入れているんですね。新十津川農業高校でも、スマート農業の授業があるそうですね。
 これまでに、水田の耕起作業を行うロボットトラクターや、収穫しながら成分分析も行うコンバインの見学、スマート農業を行っている農家さんの講義、農薬散布用ドローンの使い方などを学ぶことができました。働き手が不足し、高齢化も進みますから、スマート農業の取り組みはとても重要だと感じました。
これまでに、水田の耕起作業を行うロボットトラクターや、収穫しながら成分分析も行うコンバインの見学、スマート農業を行っている農家さんの講義、農薬散布用ドローンの使い方などを学ぶことができました。働き手が不足し、高齢化も進みますから、スマート農業の取り組みはとても重要だと感じました。

 谷本さんが所属する稲作研究班では、どのようなテーマに取り組んでいるんですか。
谷本さんが所属する稲作研究班では、どのようなテーマに取り組んでいるんですか。
 陸稲栽培を研究しています。水田栽培では、水を張った田んぼの土をさらに細かく砕き、丁寧にかき混ぜて、土の表面を平らにする代掻(しろか)きという作業があります。また、気候や成長に合わせて水田の水深を調節することも必要です。一方、陸稲は畑で栽培するため、これらの重労働から解放される利点があるんです。ただ、陸稲の場合、雨が降らないときの生育不良など、水稲にはない課題も多く、それぞれの長所、短所を把握しようとしているところです。
陸稲栽培を研究しています。水田栽培では、水を張った田んぼの土をさらに細かく砕き、丁寧にかき混ぜて、土の表面を平らにする代掻(しろか)きという作業があります。また、気候や成長に合わせて水田の水深を調節することも必要です。一方、陸稲は畑で栽培するため、これらの重労働から解放される利点があるんです。ただ、陸稲の場合、雨が降らないときの生育不良など、水稲にはない課題も多く、それぞれの長所、短所を把握しようとしているところです。

 新十津川農業高校は、近隣の子どもたちと田植えをしたり、町の人とスマート農業の勉強をしたり、地域の方との交流も深いですね。この3年間で、校外の方との交流で記憶に残っていることはありますか。
新十津川農業高校は、近隣の子どもたちと田植えをしたり、町の人とスマート農業の勉強をしたり、地域の方との交流も深いですね。この3年間で、校外の方との交流で記憶に残っていることはありますか。

 インターンシップです。卸売市場ではスーパーなどに出荷する野菜や肉の仕分けを、農機具メーカーではコンピュータで作成した図面などの見方を教わったりしました。どの職場にも輝いている大人がいて、その方々から本音を聞かせていただいたりしたことで、自分のスキルや知識、将来に対する考え方を自分なりに整理することもできました。また、自分が成長していることも感じられました。
インターンシップです。卸売市場ではスーパーなどに出荷する野菜や肉の仕分けを、農機具メーカーではコンピュータで作成した図面などの見方を教わったりしました。どの職場にも輝いている大人がいて、その方々から本音を聞かせていただいたりしたことで、自分のスキルや知識、将来に対する考え方を自分なりに整理することもできました。また、自分が成長していることも感じられました。
 来年の春には、高校も卒業です。進路は決まりましたか。
来年の春には、高校も卒業です。進路は決まりましたか。
 新十津川農業高校で学んだ農業の基礎知識を生かし、より専門的な知識や技術を身に付けられるよう、北海道立農業大学校の稲作経営専攻コースへ進学します。ふだんは深川市にある拓殖大学北海道短期大学農学ビジネス学科の学生として学び、夏・春休み期間は本別町の大学校で経営管理の授業、農家実習などの集中講義を受けることになっています。
新十津川農業高校で学んだ農業の基礎知識を生かし、より専門的な知識や技術を身に付けられるよう、北海道立農業大学校の稲作経営専攻コースへ進学します。ふだんは深川市にある拓殖大学北海道短期大学農学ビジネス学科の学生として学び、夏・春休み期間は本別町の大学校で経営管理の授業、農家実習などの集中講義を受けることになっています。
 新十津川農業高校の校訓「不撓不屈」の精神で、道を切り開いていってくださいね。では、最後に谷本さんにとってお米はどんなところが魅力かを教えてください。
新十津川農業高校の校訓「不撓不屈」の精神で、道を切り開いていってくださいね。では、最後に谷本さんにとってお米はどんなところが魅力かを教えてください。

 お米は野菜や果物と違い、長期保存ができます。だから、主食になれたんだと思いますし、お米は日本の文化の一つです。たくさんのお米を食べてほしいです。
お米は野菜や果物と違い、長期保存ができます。だから、主食になれたんだと思いますし、お米は日本の文化の一つです。たくさんのお米を食べてほしいです。

 今日はありがとうございました。
今日はありがとうございました。