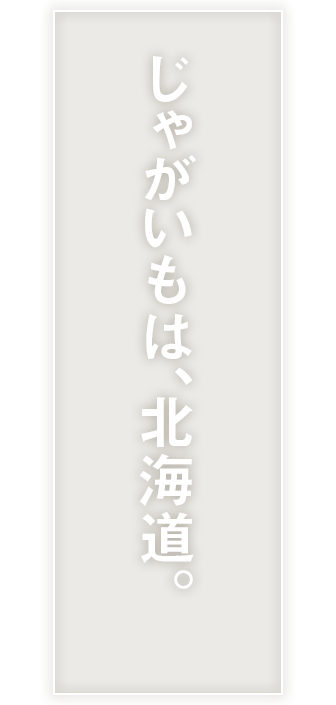
「この地発祥のメークインを守り続けたい」


トップバッターのいもはデリケート
函館市から、車で約1時間。『メークイン』の一大産地として知られる厚沢部町は、1925(大正14)年に日本で初めてメークインが栽培された発祥の地です。
「うちの畑では、いつ頃から『メークイン』を作っているのか、正確には分からないですけど、かなり昔から作り続けています(笑)」とはにかむのは、20年前に四代目として就農した山本耕平さんです。
例年7月から出荷される同町の『メークイン』は、北海道産のじゃがいもの中でもトップバッター的存在。山本さんは「〝さすが北海道産はおいしいね!〟と喜ばれるじゃがいもをいち早く届けたい意識もあり、私たちは責任とプライドを持って作っています」と力を込めます。8月中旬頃までに市場に出回る『メークイン』は、特に皮が柔らかく非常にデリケートなのだそう。そこで山本さんは収穫する際に、生卵を触るように注意深く扱うといいます。
「土からを掘り起こすのは機械ですが、一つ一つのじゃがいもを拾うのは、手作業なんです。じゃがいも同士がぶつかるだけでも傷がつき、皮もむけやすいので、とてもじゃないですが機械での収穫はできないんですよ」
-

掘り出した『メークイン』は、どれも色白の“美人”ぞろい。山本さんによると、土が黒いと、いもの色も黒くなるそう
町の誇りをブランド化で守る
見た目の美しさから、「5月(May)」の「女王(Queen)」の名が付いた『メークイン』。山本さんが現在組合長を務める「桧山南部食用馬鈴薯生産組合」では、生産者自らが大きさや形など出荷基準を厳格に定め、品質重視の栽培に力を入れています。
「『メークイン』は、表面がつるりとした細長い卵形が最も理想的な形です。私たちは、おいしさはもちろんですが、見た目にも美しいメークインづくりにもこだわっています」。同組合では、出荷時に立ち会い検査を行い、生産者が互いに出来栄えを確認しています。「ほかの生産者が作ったメークインを見ることや見られることで、品質への意識が高まります。統一した規格を安定的に出荷することで、産地としての信頼にもつながります」と山本さんは説明します。
-

メークインの花の色は紫色
出荷先は圧倒的に道外で、関東や関西、中・四国、九州まで及びます。同JAでは現在『あっさぶメークイン』という名称で、地域団体商標の登録を申請中。「産地が一丸となって、発祥の地である『あっさぶメークイン』を守っていきたいと考えています。コロナ禍で、全国各地の店頭での対面販売ができず、歯がゆい思いをしていますが、1日も早く消費者の皆さんのもとに出向いて、このおいしさを直接伝えたいです」
おいしさの決め手になるのは、じゃがいも1個当たりに含まれるでんぷん価(でんぷん量)です。山本さんは「一般的な『メークイン』はやや粘質ですが、うちの『メークイン』はでんぷんの含有量が比較的多いので、ホクホク感もあるのが特徴です。自分は、小さい頃から地元の『メークイン』しか食べたことがありませんが、おいしさには自信があります」と太鼓判を押します。
山本さんのおすすめの食べ方は「いもの塩煮」。鍋に水と塩を入れ、皮をむいたいもを水から煮て、中まで火が通ったらお湯を捨て、軽く粉吹きにすれば完成。「残ったら、オーブントースターで焼くと二度おいしいです」
今年の『あっさぶメークイン』はでんぷん価が高めで、出来が良いとのこと。市場に出回るのは、例年11月中旬までにつき、どうぞお見逃しなく!
-

畑の土は驚くほどふかふか。「一番苦労するのが土づくりです。良いいもに育つ秘けつは、土を柔らかくすることです」と山本さん
- 『メークイン』生産者 山本 耕平さん(厚沢部町)[JA新はこだて]
厚沢部町出身。農業高校卒業後、自動車販売業を経て、2001年に就農。
2019年に「桧山南部食用馬鈴薯生産組合」の組合長に就任。

