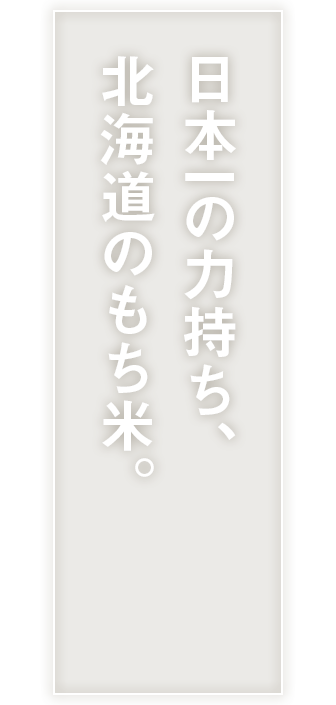
切っても切れない、日本の四季ともち食文化
おもちはなぜ、四季折々の行事やハレの日(お祝いのある特別な日)に食べられるようになったのでしょうか。ここでは、日本のもち食にまつわる豆知識を紹介します。そして、多様な食文化を育みながら、四季を通して私たちの暮らしに根付いている習わしも紐解いてみます。 (ここで紹介するもちは、うるち米の米粉で作るものも含みます。)
- 監修 : 伝承料理研究家 奥村 彪生(あやお)
1937年和歌山県生まれ。料理研究家の故・土井勝氏に25年間師事し、独立。伝統食や民俗料理、食文化の研究者として知られる。『日本めん食文化の一三〇〇年』で第一回辻静雄食文化賞受賞。『おくむらあやお ふるさとの伝承料理11 わくわくお正月とおもち』農文協刊ほか著書多数。NHK『きょうの料理』講師のほか、『美の壺(雑煮)』『チコちゃんに叱られる!』など出演多数。






