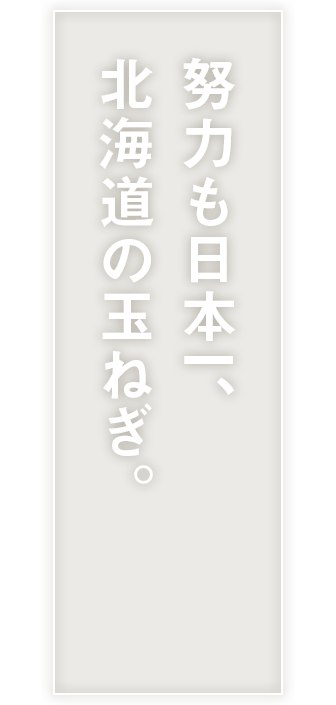
努力も日本一、北海道の玉ねぎ。
「みんなで助け合う精神が、日本一強い産地です」


天気に泣いても仲間の力が励みに
北見市や置戸町、訓子府町の3市町からなるJAきたみらい。同JAは、全国最大の玉ねぎ産地で、全道一の収穫量を誇ります(※)。
「うちらが一番なのは、収量や品質に対しての責任感が人一倍強いからだと思います」と北川裕一さん。「例えば7月に収穫する極早生の玉ねぎは柔らかいので、30度を超える日は、収穫を中止したほうがいい時があり、屋外のコンテナで保管している玉ねぎを屋内に移す必要もあります。その点に気が回らず作業に熱中している人がいると、誰ともなく注意するんです。成功例だけでなく、かつて自分が失敗したことも仲間と共有して、みんなでたくさん収穫しようという気持ちが強い人ばかりなんです」と付け加えます。
440戸の玉ねぎ生産者が所属する「きたみらい玉葱振興会」では、安定的な供給を目標に掲げています。昨年は、過去に類を見ない干ばつに苦しめられたため、会員みんなで意見を交え、今後の対策を講じたといいます。
「干ばつに負けないぐらいしっかりと丈夫な根を張れるよう、土づくりを見直し、米ぬかや堆肥など有機質を畑にまくように周知しました」と北川さん。「個人的には、十分な水やりができなかったことが反省点です。不眠不休で水やりをしなければならないほどハードな状況に、自分は対応ができなかったんです。周りでも収量が落ち込んだ人は多いですが、水を一晩中まいて頑張った人は収穫できているんですね。あの悔しさを思うと、睡眠を削ってでもやっておけばよかったと、今なら思えます」。
北川さんは、「天気にはいつも泣かされます」と言いながら、失敗を繰り返さないことが肝心と前を向きます。
※農林水産省「野菜生産出荷統計」2020年より
-

玉ねぎは生長が進むと、葉が次々と倒れていきます。この倒伏が始まると、収穫作業の準備段階に入ります
実力が評価され天皇杯を受賞
「きたみらい玉葱振興会」は、昨年(2021年)秋に農林水産省などが主催する、第60回農林水産祭で最高賞の天皇杯を受賞しました。
「一番高く評価されたのは、質と量の向上を目指して、8地区が切磋琢磨して収量を伸ばしてきたこと。そして若手生産者との連携で技術が継承されていること。その根底にあるのが、みんなで助け合う土地柄です。助け合いの精神が受賞につながったと思います」と北川さん。「目に見える評価をいただけたことで、自分の子どもが〝お父さんすごいね!〟って喜んでくれたんです。それが、何よりもうれしかったですね」と笑顔を見せます。
振興会では、品質を維持するために、選果基数に対し一定数の正品を抽出し、現品審査を行っています。出荷前の玉ねぎの色や汚れなど品質確認を行い、生産者個々に審査結果を通知することで品質の高位平準化を図っています。
「現品審査の効果として、品質に対する意識が向上し、常にいいものを作ろうとみんなが頑張って、それぞれが高品質な玉ねぎを取れるようになりました。誰かがいい仕事をしていたら、みんなが真似をするんです。最近は、玉ねぎの定植が終わったらこまめに除草機を動かしたり、畑が乾燥気味の時は水をまいてみたり。そんなことをしていたら、あっという間に収穫です。昔と比べると暇がなくなってしまいましたが、そうした積み重ねが品質の向上につながっていると思います」
最後に今シーズンの出来を尋ねたところ、「今年は今のところ順調に育っていて、このままいけばおいしい玉ねぎがたくさんできると思います。楽しみに待っていてください!」と頼もしい言葉が返ってきました。
北海道NOW:JAきたみらい「日本一の玉ねぎ産地の集出荷施設」の記事はこちらから >
-

収穫作業は、晴天が続く日に行うのが理想的。収穫後は玉ねぎを数日ほど畑で乾燥させます
- 『玉ねぎ』生産者 北川 裕一さん[ JAきたみらい ]
1968年北見市生まれ。会社員を経て、32歳で四代目として就農。現在は玉ねぎ(玉ねぎ、赤玉ねぎ、サラダ玉ねぎ、環境保全型玉ねぎ)、小麦、てん菜を栽培。2019年に「きたみらい玉葱(たまねぎ)振興会」の副会長に就任。

