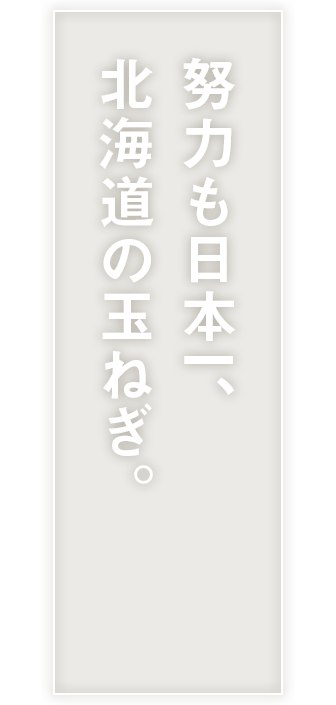
努力も日本一、北海道の玉ねぎ。
「環境に配慮した玉ねぎを選ぶ人が、
少しでも増えたらうれしいです」


- 『玉ねぎ』生産者 山内 秀之さん[ JAきたみらい ]
北見市生まれ。農業系の短期大学を卒業後、1985年に三代目として就農。現在は玉ねぎ(玉ねぎ、赤玉ねぎ、サラダ玉ねぎ、環境保全型玉ねぎ)、小麦、てん菜、じゃがいもを栽培。今年2月に「きたみらい玉葱振興会 クリーン栽培玉葱部会」の部会長に就任。
MENU
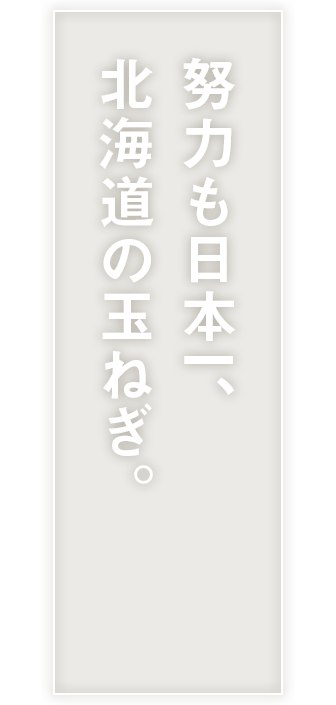
努力も日本一、北海道の玉ねぎ。


JAきたみらいでは、化学肥料や化学合成農薬の使用を削減し、環境に配慮した栽培基準で育てる「環境保全型玉ねぎ」の生産にも取り組んでいます。
山内秀之さんが環境保全型玉ねぎを作り始めたのは15年ほど前。
「当時は、産地偽装など食の安全性が社会問題になっていました。安全・安心な農産物を作ろうという動きがこの地域で起こり、自分もやってみたいと思ったのがきっかけです」
栽培基準は、肥料が北海道基準の5割、農薬は3割以上削減。「化学肥料は半減しなければならないのですが、有機質の肥料は継続して投入する決まりがあるんです。そうした土づくりも含めて、部会が一丸となって取り組んでいます」。
山内さんが部会長を務める「きたみらい玉葱振興会 クリーン栽培玉葱部会」には、80戸の生産者が所属。全員が「持続農業法」に基づいて都道府県知事が認定した、堆肥などを使った土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う農業者「エコファーマー」の資格を取得しています。最近は肥料などの資材が高騰していますが、厳しい栽培基準で育てることがコストの削減、そして自分たちの生活を守ることにもつながっていると山内さんは感じています。

玉ねぎの作付面積は約12haで、環境保全型は8.5haを占めるそう。「肥料も農薬も抑えている分だけ、神経を使います。生育ステージに合わせた対策は常に頭の中にありますが、大切なのは注意深く作物を観察すること」と山内さん
環境保全型玉ねぎの大きな特徴は、農作業での二酸化炭素の排出を削減する、カーボン・オフセットへの取り組みです。カーボン・オフセットとは、企業や団体が地球温暖化対策として二酸化炭素排出量を減らす努力をした上で、どうしても削減できない量を、ほかの場所で削減・吸収した分から買い取ることで埋め合わせることをいいます。
「クリーン栽培玉葱部会」では、化学肥料・農薬の使用量を抑制させることで、施肥・防除にかかる機械作業を縮小。農作業での二酸化炭素の排出量を削減しています。
「玉ねぎを生産する上で、トラクターなど機械の使用は不可欠で、二酸化炭素の排出は避けられません。今あらゆる産業がカーボン・オフセットに取り組む中で、農業も食の供給だけでなく、どれだけ環境問題に貢献できるのか、自分たちも考えながら取り組んでいます」
また、「クリーン栽培玉葱部会」では、売り上げの一部を道内の森林保全活動の資金として提供することで、生産工程での二酸化炭素排出量を埋め合わせしています。消費者はこの玉ねぎを購入することで、環境保全活動に貢献できるメリットがあります。
「ここまで大きな組織が一丸となって環境保全に取り組んでいる農作物は、北海道内でもほかに類がないと思います。これまでにない、新しい考え方ということもあり、部会としても、環境に関する講習会など勉強できる機会を設けていけたらと考えています」と山内さんは力を込めます。
取り組みへの共感の輪も広がっており、この9月からは名古屋市の小学校の学校給食約12万食に、環境保全型玉ねぎの供給が始まりました。同市では、この玉ねぎをSDGsの実践事例として、小学校での食育指導にも活用する予定だそうです。
「環境に配慮した商品を選ぶ人が少しでも増えたらうれしいです。この玉ねぎが主流になる未来に向けて、我々は若い生産者が続々と参加したくなるような、魅力ある組織を築いていきたいです」と山内さんは笑顔で語りました。
農家の時計:JAきたみらい「環 玉ねぎ」の記事はこちらから >

堆肥には、近郊の農家から排出される牛のふんなどを活用。環境負荷の軽減にもつながっています
北見市生まれ。農業系の短期大学を卒業後、1985年に三代目として就農。現在は玉ねぎ(玉ねぎ、赤玉ねぎ、サラダ玉ねぎ、環境保全型玉ねぎ)、小麦、てん菜、じゃがいもを栽培。今年2月に「きたみらい玉葱振興会 クリーン栽培玉葱部会」の部会長に就任。