北海道大野農業高等学校 北口 大智さん
北海道大野農業高等学校は、北海道新幹線「新函館北斗」駅がある北斗市の大野地区で、約80年の歴史を刻む伝統校。農業科、園芸科、食品科学科、生活科学科があり、生徒たちは専門の学びを深めるとともに、4科連携で農業の課題に積極的に取り組んでいます。
北海道大野農業高等学校
041-1231 北斗市向野2丁目26番1号
http://www.oononougyou.hokkaido-c.ed.jp/
TEL:0138-77-8800
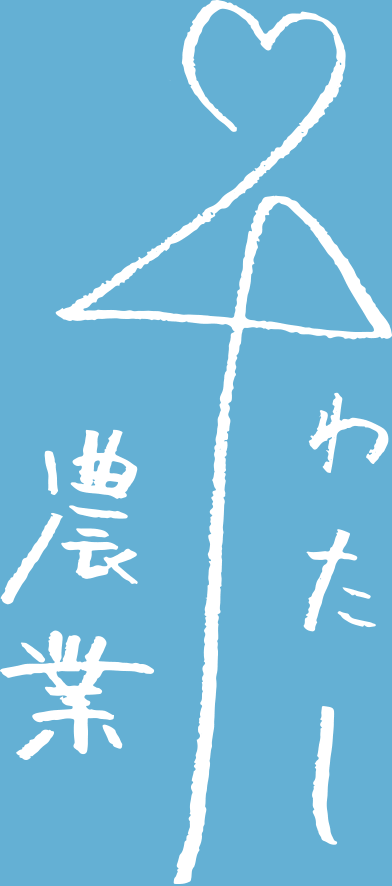
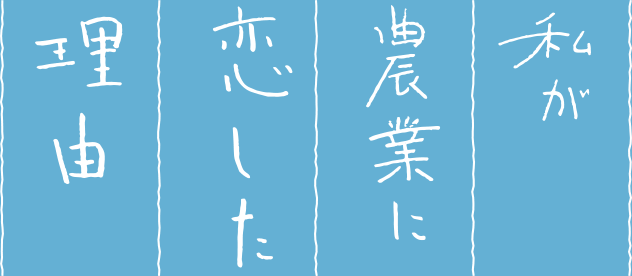

北海道大野農業高等学校は、北海道新幹線「新函館北斗」駅がある北斗市の大野地区で、約80年の歴史を刻む伝統校。農業科、園芸科、食品科学科、生活科学科があり、生徒たちは専門の学びを深めるとともに、4科連携で農業の課題に積極的に取り組んでいます。
北海道大野農業高等学校
041-1231 北斗市向野2丁目26番1号
http://www.oononougyou.hokkaido-c.ed.jp/
TEL:0138-77-8800

北口さん
GREEN編集室
![]() 北口さんは、北海道でも屈指の米どころ・蘭越(らんこし)町の出身と聞きました。
北口さんは、北海道でも屈指の米どころ・蘭越(らんこし)町の出身と聞きました。
 はい。実家では、祖父母と両親が米をつくっています。東京ドーム2個分以上の11ヘクタールの水田で、「ゆめぴりか」、「ななつぼし」、「きたくりん」の3品種を栽培しています。
はい。実家では、祖父母と両親が米をつくっています。東京ドーム2個分以上の11ヘクタールの水田で、「ゆめぴりか」、「ななつぼし」、「きたくりん」の3品種を栽培しています。
![]() 蘭越町から大野農業高等学校へ入学されたのは、どうしてですか。かなり離れていますよね。ちょっと調べたら、車で約3時間とか。
蘭越町から大野農業高等学校へ入学されたのは、どうしてですか。かなり離れていますよね。ちょっと調べたら、車で約3時間とか。

 地元の蘭越では、2011年から、米の食味日本一を決める「米-1(コメワン)グランプリ」を開催していて、僕が中学生の頃、大野農業高等学校の水稲班が参加していることを知り、興味を持ったのがきっかけです。
地元の蘭越では、2011年から、米の食味日本一を決める「米-1(コメワン)グランプリ」を開催していて、僕が中学生の頃、大野農業高等学校の水稲班が参加していることを知り、興味を持ったのがきっかけです。
![]() 大野地区は、江戸時代に米が収穫されていたという記録がある「北海道の水田発祥の地」でもあります。米づくり一筋の北口家に育った大智さんとは、縁があったのかもしれませんね(^o^)
大野地区は、江戸時代に米が収穫されていたという記録がある「北海道の水田発祥の地」でもあります。米づくり一筋の北口家に育った大智さんとは、縁があったのかもしれませんね(^o^)

 将来、「米-1グランプリ」で入賞できる米をつくりたいという気持ちが高まって、家を離れることになりますが、思い切って入学し、農業科の水稲班を選びました。
将来、「米-1グランプリ」で入賞できる米をつくりたいという気持ちが高まって、家を離れることになりますが、思い切って入学し、農業科の水稲班を選びました。

![]() そもそも、米づくりのどんなところに興味を持ったんですか。
そもそも、米づくりのどんなところに興味を持ったんですか。
 祖父母や両親の仕事を見ていて、工夫次第で手間が省けたり、収量を増やしたりできることを知り、自分次第というところがいいなと。
祖父母や両親の仕事を見ていて、工夫次第で手間が省けたり、収量を増やしたりできることを知り、自分次第というところがいいなと。
![]() 入学の動機にも感じたのですが、北口さんは自立心が強いんですね。これまで学校の水田で米づくりのひと通りを学んでいるようですが、自分で作業をしてみて、ご家族の様子を見ていた時とは違う感想を持ちましたか。
入学の動機にも感じたのですが、北口さんは自立心が強いんですね。これまで学校の水田で米づくりのひと通りを学んでいるようですが、自分で作業をしてみて、ご家族の様子を見ていた時とは違う感想を持ちましたか。

 季節ごとに作業が異なり、メリハリがあるところがおもしろいです。水稲班は、道南生まれの品種「ふっくりんこ」の生産者でつくる「函館育ち ふっくりんこ蔵部(くらぶ)」の栽培生産出荷基準を満たす米づくりを目指しています。そのため、施肥量の遵守など、気を付けなければいけないことがいくつもありますが、適期作業が一番大事だと実感しています。
季節ごとに作業が異なり、メリハリがあるところがおもしろいです。水稲班は、道南生まれの品種「ふっくりんこ」の生産者でつくる「函館育ち ふっくりんこ蔵部(くらぶ)」の栽培生産出荷基準を満たす米づくりを目指しています。そのため、施肥量の遵守など、気を付けなければいけないことがいくつもありますが、適期作業が一番大事だと実感しています。

![]() 7月下旬から8月にかけては、どのような作業を行うんですか。
7月下旬から8月にかけては、どのような作業を行うんですか。
 殺虫・殺菌剤を散布して、品質と収量を落とさないようにする防除作業がメインです。夏休み期間中は、水稲班の班員が交替で生育調査も行います。今年も「米-1グランプリ」に参加予定で、入賞を目指して、みんなで頑張っているところです!
殺虫・殺菌剤を散布して、品質と収量を落とさないようにする防除作業がメインです。夏休み期間中は、水稲班の班員が交替で生育調査も行います。今年も「米-1グランプリ」に参加予定で、入賞を目指して、みんなで頑張っているところです!

![]() おいしい米がとれますよ、きっと(^o^)V
おいしい米がとれますよ、きっと(^o^)V
 「ふっくりんこ」は、道南の生産者の方々が長年大切に育ててきたブランド米ですから、僕たちもその想いを感じながら、一生懸命やっています。
「ふっくりんこ」は、道南の生産者の方々が長年大切に育ててきたブランド米ですから、僕たちもその想いを感じながら、一生懸命やっています。

![]() 頼もしい!大野農業高等学校は、地域のつながりが深そうですね。
頼もしい!大野農業高等学校は、地域のつながりが深そうですね。
 はい。今年の5月下旬には、僕ら水稲班6人で、北斗市立市渡(いちのわたり)小学校の3年生10人に田植えを教える、交流授業がありました。
はい。今年の5月下旬には、僕ら水稲班6人で、北斗市立市渡(いちのわたり)小学校の3年生10人に田植えを教える、交流授業がありました。

![]() 子どもたちは、どんな様子でしたか?
子どもたちは、どんな様子でしたか?
 はじめのうちは、田んぼの中に入るのを嫌がっている子もいましたが、だんだん慣れて、最後はとても楽しそうに作業をしていました。農業が好きになってくれたらいいなぁと、心から思いました。
はじめのうちは、田んぼの中に入るのを嫌がっている子もいましたが、だんだん慣れて、最後はとても楽しそうに作業をしていました。農業が好きになってくれたらいいなぁと、心から思いました。
![]() 勉強、米づくり、部活、地域の方々との交流と、毎日が充実していますね。卒業後は、どうされるんですか。
勉強、米づくり、部活、地域の方々との交流と、毎日が充実していますね。卒業後は、どうされるんですか。
 実家に帰って、米をつくります。グローバルGAP(ギャップ)も取得したいと考えています。
実家に帰って、米をつくります。グローバルGAP(ギャップ)も取得したいと考えています。
![]() 2018年、大野農業高等学校は、全道の農業高校で初めて、米のJGAP(ジェイギャップ)認証を日本GAP協会から取得していますね。
2018年、大野農業高等学校は、全道の農業高校で初めて、米のJGAP(ジェイギャップ)認証を日本GAP協会から取得していますね。

 JGAPは食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられるもので、適切に管理されている環境だからこそ、そこでつくられる農産物は安全ですよというお墨付き。グローバルGAPはドイツの法人が認証するもので、おおまかに言うと、これを取得すると、僕がつくった米が安全で品質の良い農産物であると、世界的に認めてもらえるんです。
JGAPは食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられるもので、適切に管理されている環境だからこそ、そこでつくられる農産物は安全ですよというお墨付き。グローバルGAPはドイツの法人が認証するもので、おおまかに言うと、これを取得すると、僕がつくった米が安全で品質の良い農産物であると、世界的に認めてもらえるんです。
![]() 蘭越町でつくった北口さんの米が海外へ!その可能性が広がるんですねp(^^)q
蘭越町でつくった北口さんの米が海外へ!その可能性が広がるんですねp(^^)q
 安全安心な米をつくることは、生産者・消費者・地域・地球環境を守ることにつながると思います。国内はもちろん、海外でも勝負できる米をつくりたい。それが目標です。
安全安心な米をつくることは、生産者・消費者・地域・地球環境を守ることにつながると思います。国内はもちろん、海外でも勝負できる米をつくりたい。それが目標です。
![]() いいお話に元気をもらいました。まずは、この秋の「米-1グランプリ」、頑張ってください。応援しています!
いいお話に元気をもらいました。まずは、この秋の「米-1グランプリ」、頑張ってください。応援しています!