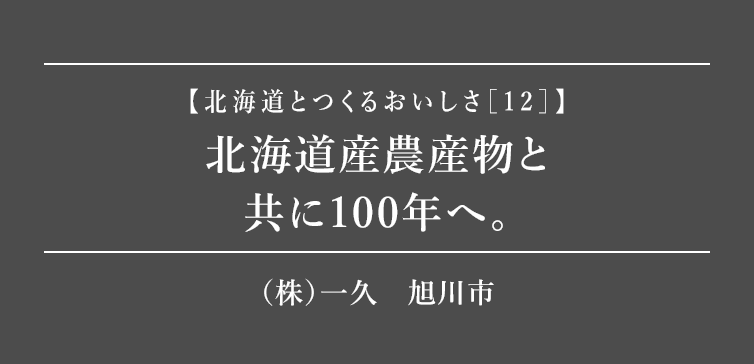北海道第二の都市・旭川市で創業し、来年100周年を迎える(株)一久(いちきゅう)。看板商品は、屋号「もち処一久大福堂」にもある大福で、北海道米と北海道産小豆で作り続けています。店頭には、おはぎ、だんご、まんじゅう、そして若き菓子職人たちが切磋琢磨し、世に送り出した渾身の品々が並び、一久のおいしさが広がりを見せています。「伝統とは、革新の連続」と言われます。期待を裏切らない味を常に提供するために、同社が守り続けていること、挑戦していることなどを聞きました。
関東大震災の日に営業許可証を取得
(株)一久の創業者は、石川県出身の久木彦左衛門さん。久木さんは、本州と北海道を日本海経由で結ぶ北前船のルートで小樽に入植し、旭川に第七師団が設置されるタイミングに合わせて、将来の発展を見越して旭川に転居。移動が多い兵隊さんには餅類が重宝されていたことから、久木さんは旭川中心部と師団を結ぶ通り沿いに一久大福餅本店を開きました。営業許可証を得たのは、ちょうど関東大震災に見舞われた日だそうです。大正、昭和、平成、令和と餅づくり一筋に暖簾を守り、約100年。現在は、旭川、札幌を中心に14店舗を構えています。

毎日さわって、塩梅を覚える
「子どもの頃は、自宅に工場があって、祖父や母がベルトコンベア並みの勢いで餡を包んだ大福をまるめる作業を手伝ってから登校しました」と振り返る久木利弘(ひさき・としひろ)代表取締役社長(写真右)。「かつては家庭で餅をついていて、家ごとに餅へのこだわりがありました。若い頃はお客さまから、“餅とは”とよく聞かされました(笑)」。久木社長のお話を興味深く聞いていた側和矩(がわ・かずのり)副主任(写真左)は、製造工程長の立場からこう語ります。「私はこの仕事を始めて18年になります。その間、米を蒸す道具が木製のせいろから樹脂の蒸し器に変わるなどの変化はありましたが、米のかたさは私たち職人の手と指先の感覚で探るなど、昔ながらの部分も少なくありません」。
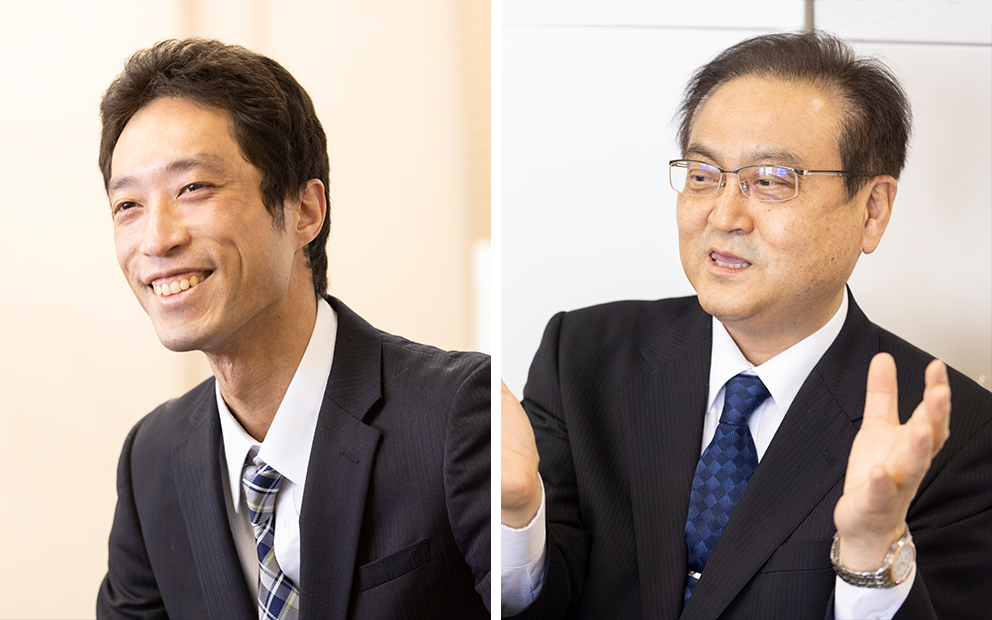
もち米、小豆、バターなど北海道産を拡大
「餅の命は、もち米です。当社では北海道産、中でも本店のある旭川から近い名寄や士別でとれる『はくちょうもち』と『風の子もち』を使っています。どちらの品種もやわらかさが長持ちし、粘りが強いので、大福にはもってこいです。なにより、もち米団地で作っているので安心ですしね」と久木社長。もち米団地とは、うるち米の混入を防ぐために、各地域内でもち米のみを栽培する生産方式です。「小豆は言うまでもなく、大福に使う黒豆やいんげん豆、かぼちゃ、まんじゅうやカステラなどに使う小麦、バターなども北海道産です。いまは道内の酪農家さんは大変な状況ですから、私たちも乳製品をもっと使っていくべきだろうと、いろいろと考えを巡らせているところです」。

餅のかたさは、餡の種類などで変える
北海道産の恵みと、伝統を受け継ぐ職人の技術で作る同社の大福は、季節限定を含めて常時8種類。側副主任は、「餅のかたさは、豆などの混ぜるものや、餡の種類によって変えています。この微妙な塩梅は、毎日のように作っている職人でないとわかりません」と説明します。「製品によって多少の工夫はしていますが、基本的な製法はずっと変えていません。餅屋の餅らしいねという声が励みになります」と久木社長。工夫といえばと、こんな話も教えてくれました。「いちご大福のいちごは、出始めの頃は餡にくるまれていましたよね。せっかくなら見えたほうがいいだろうと、当社では餅生地をはさみ菊という手法をヒントに切って、いちごを見えるようにのせました」。

「きらら397」の登場から生まれた味
「北海道米の『きらら397』の登場によって、だんごをよりおいしく作ることができるようになりました」。久木社長はその経緯をこう語ります。だんごには上新粉(米粉)を使っていましたが、久木社長は幼い頃、茶碗の残りご飯を箸でつつき、丸めて食べた味が忘れられずにいました。「きらら397」と出会ったことで、その頃のことを思い出し、「きらら397」を蒸かして臼にいれ、ついてみました。しかし、だんごにはなりません。そこで赤飯づくりの蒸し工程とおはぎづくりの蒸し工程を応用してみたところ、納得のいくだんご生地ができたそうです。「粉を使用するより工程に手間がかかります。でも、米で作っただんごは味にくせがなく、自然なおいしさを楽しめます。いまは『ななつぼし』に切り替えましたが、製法は変えていません」。

1級菓子製造技能士らによる
オリジナル商品
おいしさづくりに真摯に取り組む同社には、「若獅子会」というグループがあります。側副主任のように、国家試験の中でも難易度の高い1級菓子製造技能士の有資格者らの集まりで、このメンバーがオリジナル商品を次々生み出しています。第1号は「ぽぬぐるシマエナガ」(写真右)で、「雪の妖精」とも称される野鳥・シマエナガをモチーフにした洋風まんじゅう。やさしい甘さのバター餡のまんじゅうをホワイトチョコレートでくるんだもので、同社初のお土産菓子でもあります。第2号が新たなチャレンジとして開発した「北海道加須底羅(ホッカイドウカステラ)」(写真左)で、しっとりプルッとした食感と、やさしい甘さを楽しめるように丁寧に焼き上げています。この2品でも、北海道産の小麦、バターがおいしさを支えています。

初めてづくしの
ホクレン新製品「まるっ恋」
側副主任が手掛けたのが、この春ホクレンくるるの杜から発売された「まるっ恋」。北海道米「ななつぼし」と北海道のミルクで作っただんごに野菜や果物などの餡をのせた“北海道ごちそう団子”です。「私はだんごを長年担当していますが、ミルクとの組み合わせは慣れていなかったので、温度調節や機材の扱いなどはデータをこまめにとるなど、慎重に臨みました」と側副主任。満足のいくだんごが完成したところで、次は餡を絞るというハードルが待っていました。「当社には、餡を絞る工程が必要な商品はありませんでしたから、餡のかたさと絞り具合のかねあいなどを徹底的に研究しました。この経験を生かして、今後は季節によって異なる餡を作るなど、バリエーションを広げる依頼があったら嬉しいです」。

北海道産農畜産物は北海道ブランド
「米に限らず、北海道の恵みは生産者の皆さん、研究機関などのおかげで進化を続けています。地元の我々はもちろん、菓子店の多くは北海道産の原材料を活用してると思います。いまや、北海道産農畜産物は北海道ブランドそのものです。そうした豊かな恵みを楽しく、明るく、元気がでるお菓子にかえて、全国の皆さまにお届けすることが使命です」と久木社長。一方、側副主任も「北海道の生産者の皆さんから原材料をお預かりし、その高い品質をきちんと消費者に伝えていく。私たちのそうした役目を果たすために、これからもしっかりした仕事をしていきます」とメッセージを寄せてくれました。
もっとおいしい商品で生産者の思いまでも伝えようとする
お二人の言葉に、作り手の誇りを感じました。
伝統と革新の物語の続きに期待しています。
> (株)一久