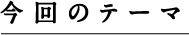
仲間とともにあるチーズ
~村上牧場ミルク工房レプレラ~

アイヌ語の「セタルペシュペナイ」(犬が泳ぎ渡る川)が略された「セタナイ」を語源とするせたな町。そのせたな町が面する日本海を一望できる山の上に、村上牧場はある。
ブラウンスイス種とジャージー種を放牧で飼育し、その乳からチーズをつくるのは村上牧場の三代目村上健吾君。
「今年は、やっと落ち着いて、自分の一番つくりたいハードタイプの『カリンパ』を仕込めているんですよ」。その笑顔に、ここ数年の忙しさから日常を取り戻した安ど感が感じられる。
ともすれば、酪農形態は、「放牧、小規模=素晴らしい」「舎飼い、大規模=工業生産的」という白黒をつけられることもある。夏季は昼夜放牧を行う健吾君だが、いつもその線引きにあてはめられないよう言葉を選んでいるという。
「例えば、都会のマンションに住む人もいれば、田舎に住む人もいる。どちらも生き方であり、正解はひとつじゃない。牛を外で飼うのも、牛舎内で飼うのも、穀物をやる、やらないということも同じ。僕はこの場所で、この環境や地域資源の中で、僕らしい生き方ってなにかと考えたときに、このやり方を選んだだけなんです」
健吾君は、牧場を継ぐために実家に戻ったとき、自分にしかできない生き方を、とギラギラしていたわけではなかったという。「そんなに自己肯定感が強い若者ではなかったですね」と笑いながらも、この土地らしさを考え、放牧を選択。その試行錯誤の毎日も、近隣地域に、つくっているものは違えど、地域を大事にする未来志向の生産者仲間がいたことが、挑戦を続けられた原動力になっている。
「放牧は難しいですよ。ちょっと目を離せば雑草がはえてきちゃうし」。きれいに整った放牧地を歩きながら健吾君は言う。
「映画のロケ地になり、たくさんの人が牧場を訪れてくれました。『えっ、牛も飼いながら、チーズもつくっているんですね』と驚かれる方も多く、でもそれがある意味一般的な認識なんだろうなと勉強になりました」
「僕は、大したチーズの種類もつくっていないし、製造量も限られている。だから、『チーズないですか?』と聞かれたら、長万部にはこういう作り手が、黒松内に行ったらこういうチーズ職人が、ニセコには、洞爺湖には・・・と、とにかく近くの友人の作り手のことばかり紹介しています。自分が売れたい、自分が有名になりたい、自分のやり方がよいことを伝えたいのではなく、仲間のチーズの作り手のことをも知ってもらい、北海道のチーズ、北海道の酪農の応援団を増やして、未来に向けて一緒に支えあっていけたらいいなと」
せたな町には、北海道のナチュラルチーズづくりの始まりを語るに欠かせない「こんどうチーズ牧場」の近藤恭敬さんという方がいた。近藤さんの灯したチーズのあかりが、この町に、仲間たちとともに引き継がれている。



